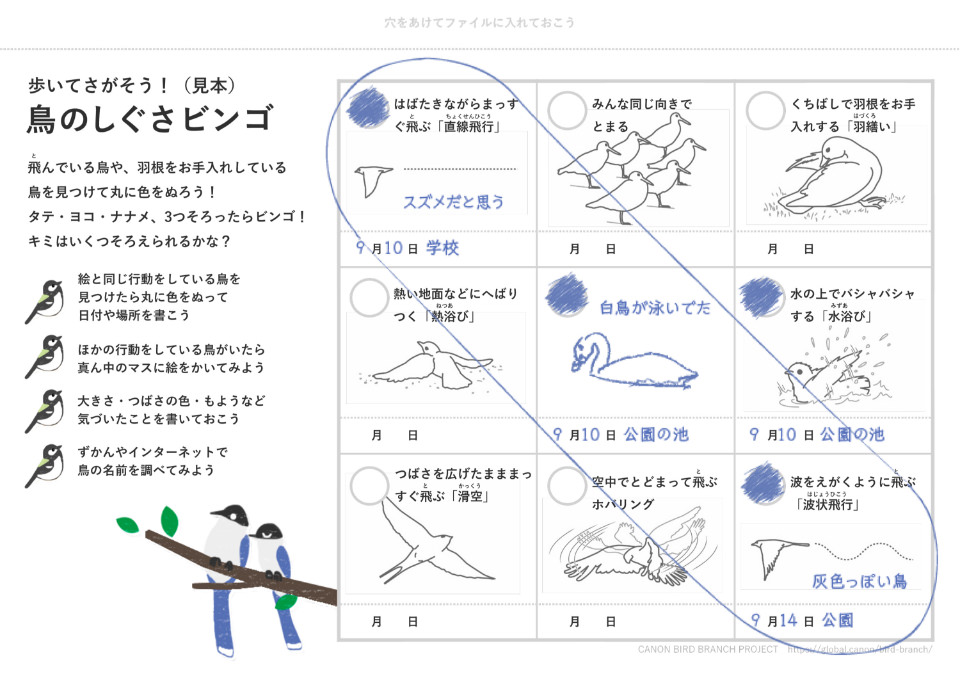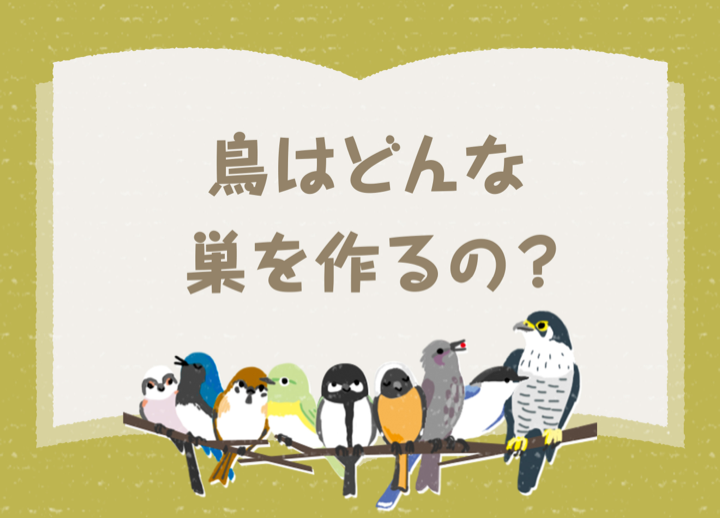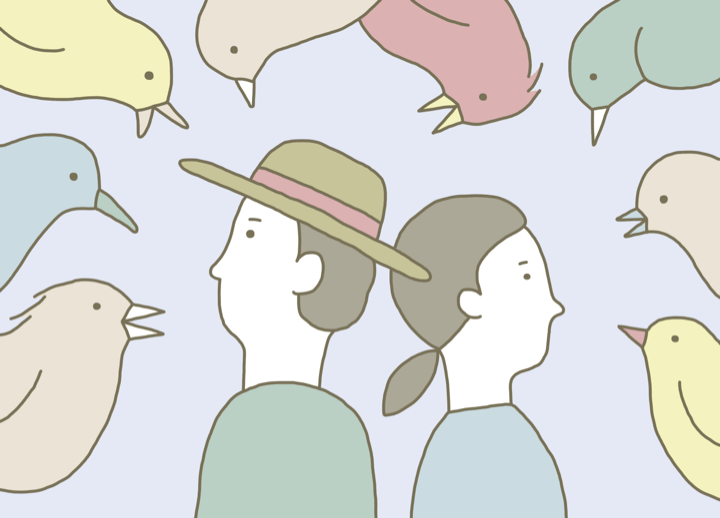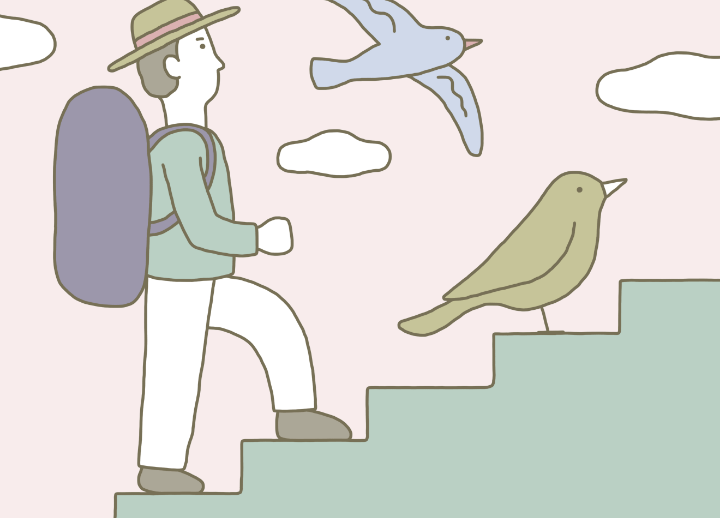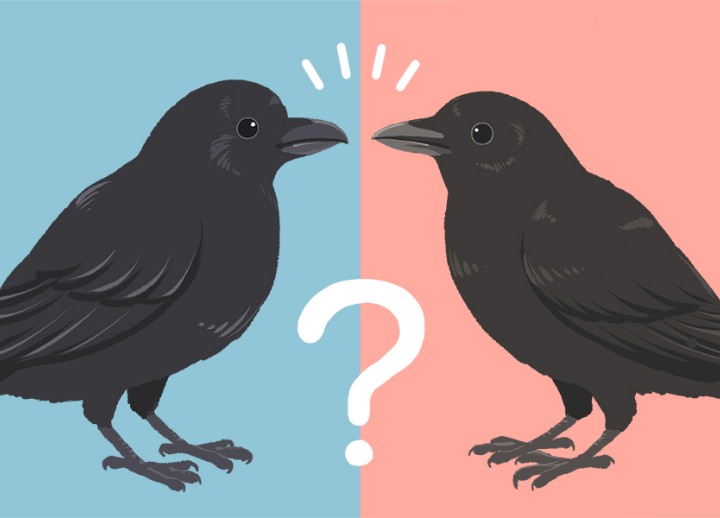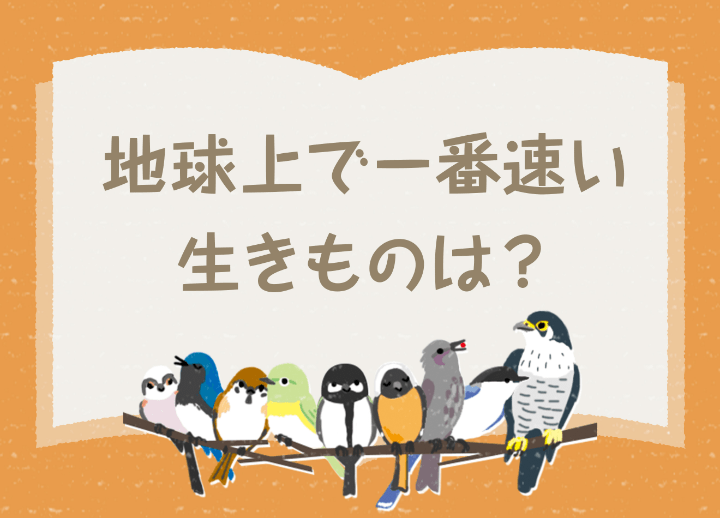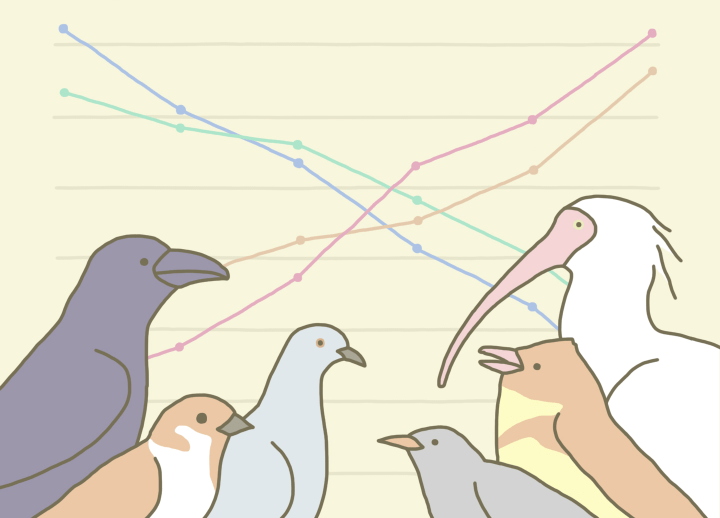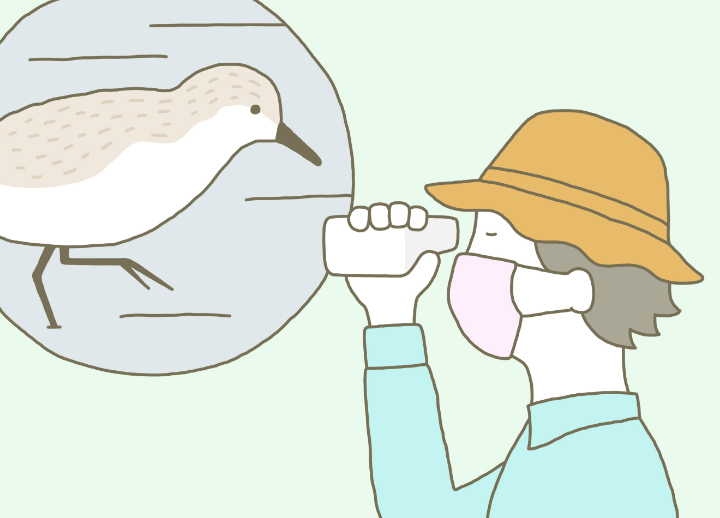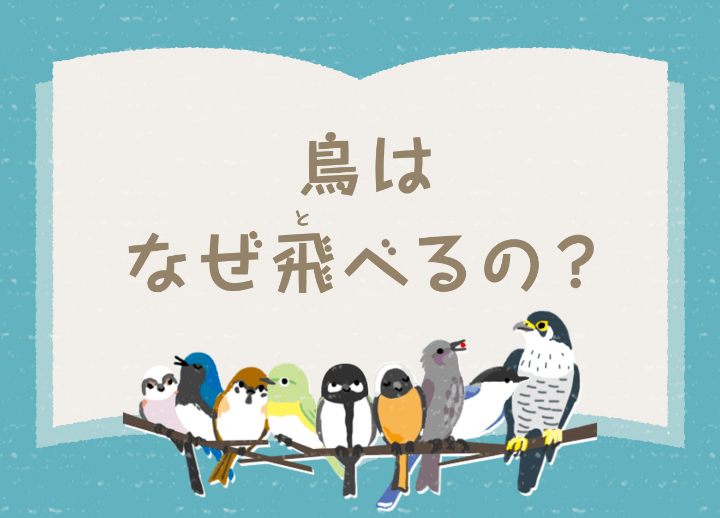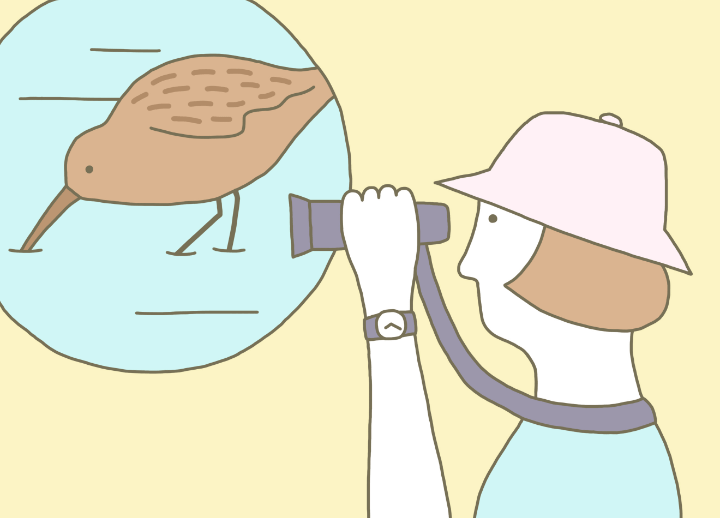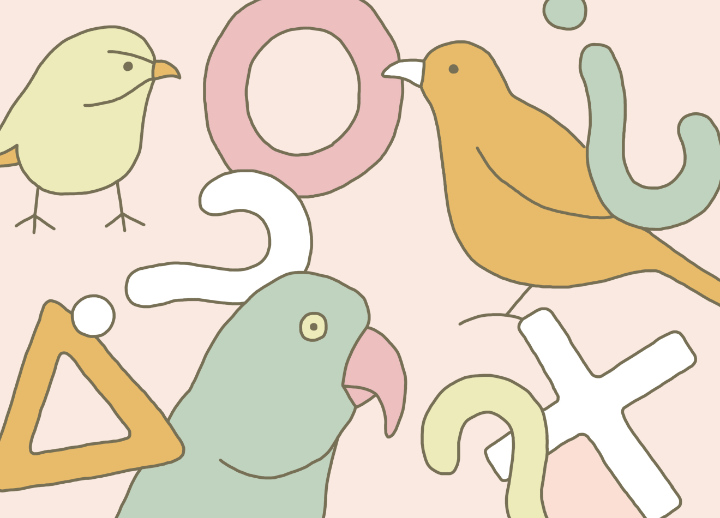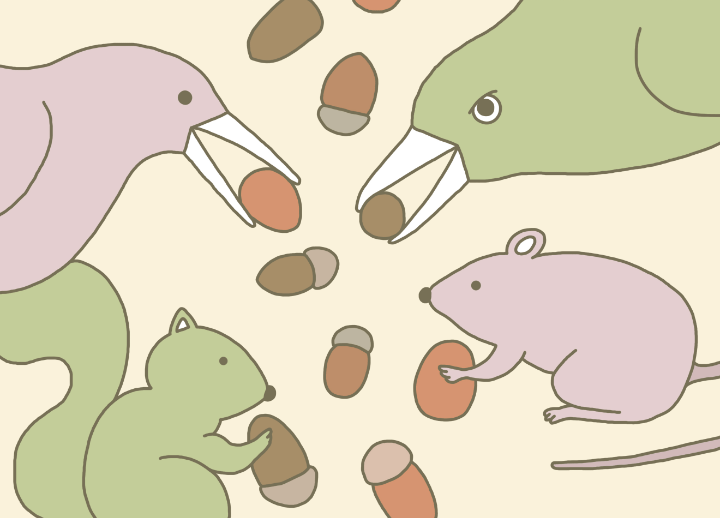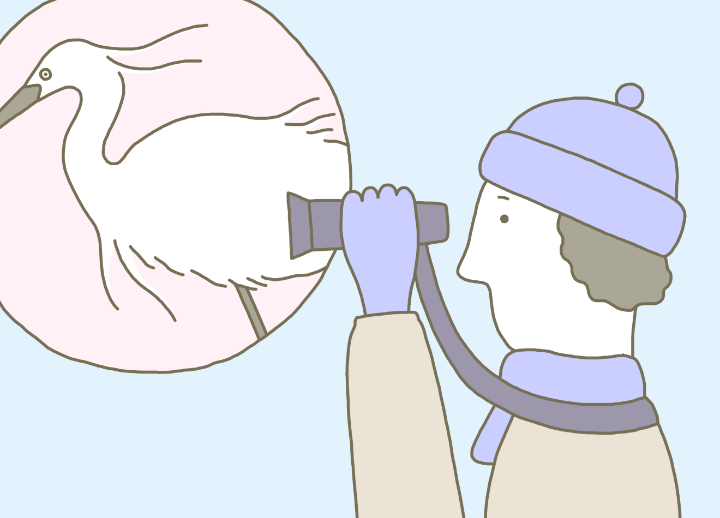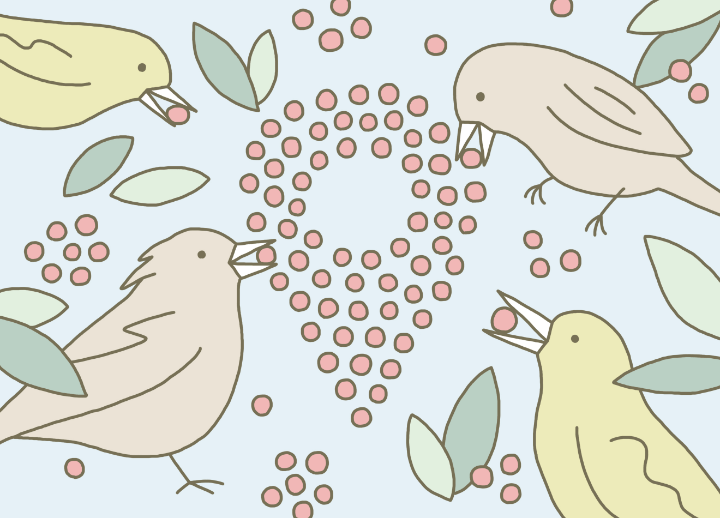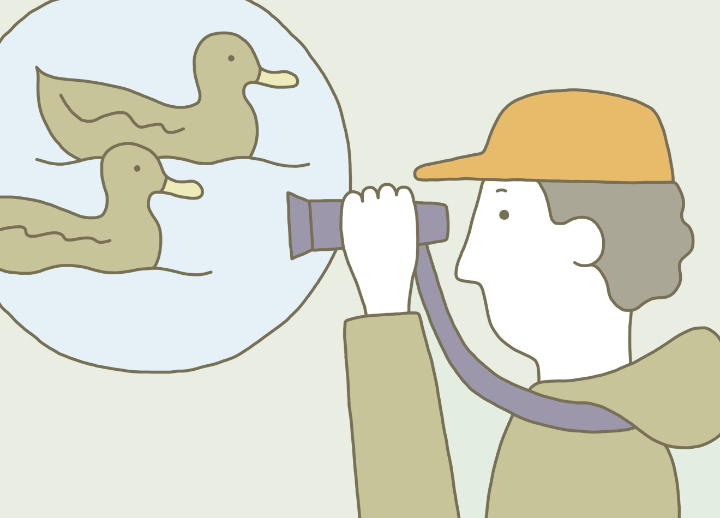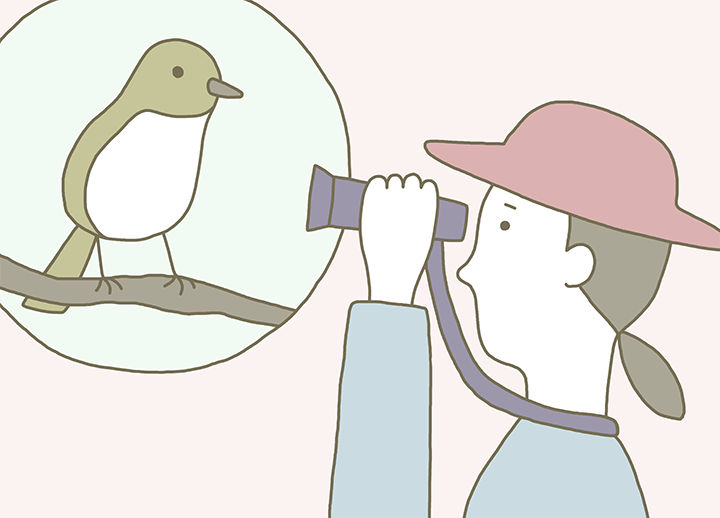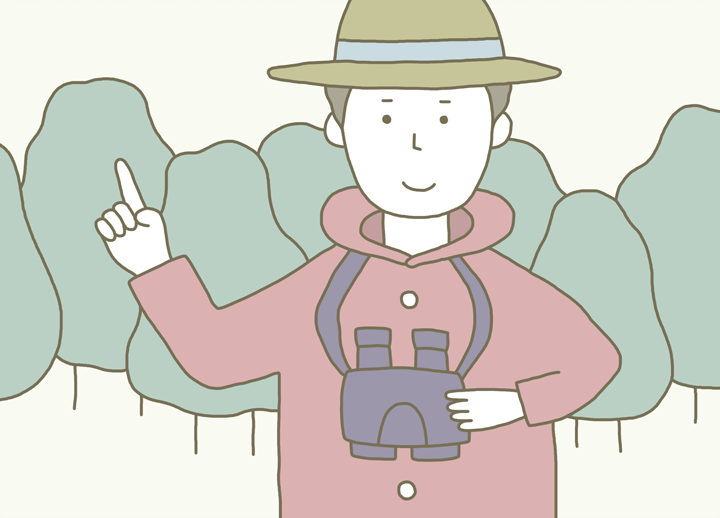鳥のヒミツをときあかせ vol.2
鳥はなぜ飛(と)べるの?
もっと知りたい!羽根のはたらきと飛び方のヒミツ
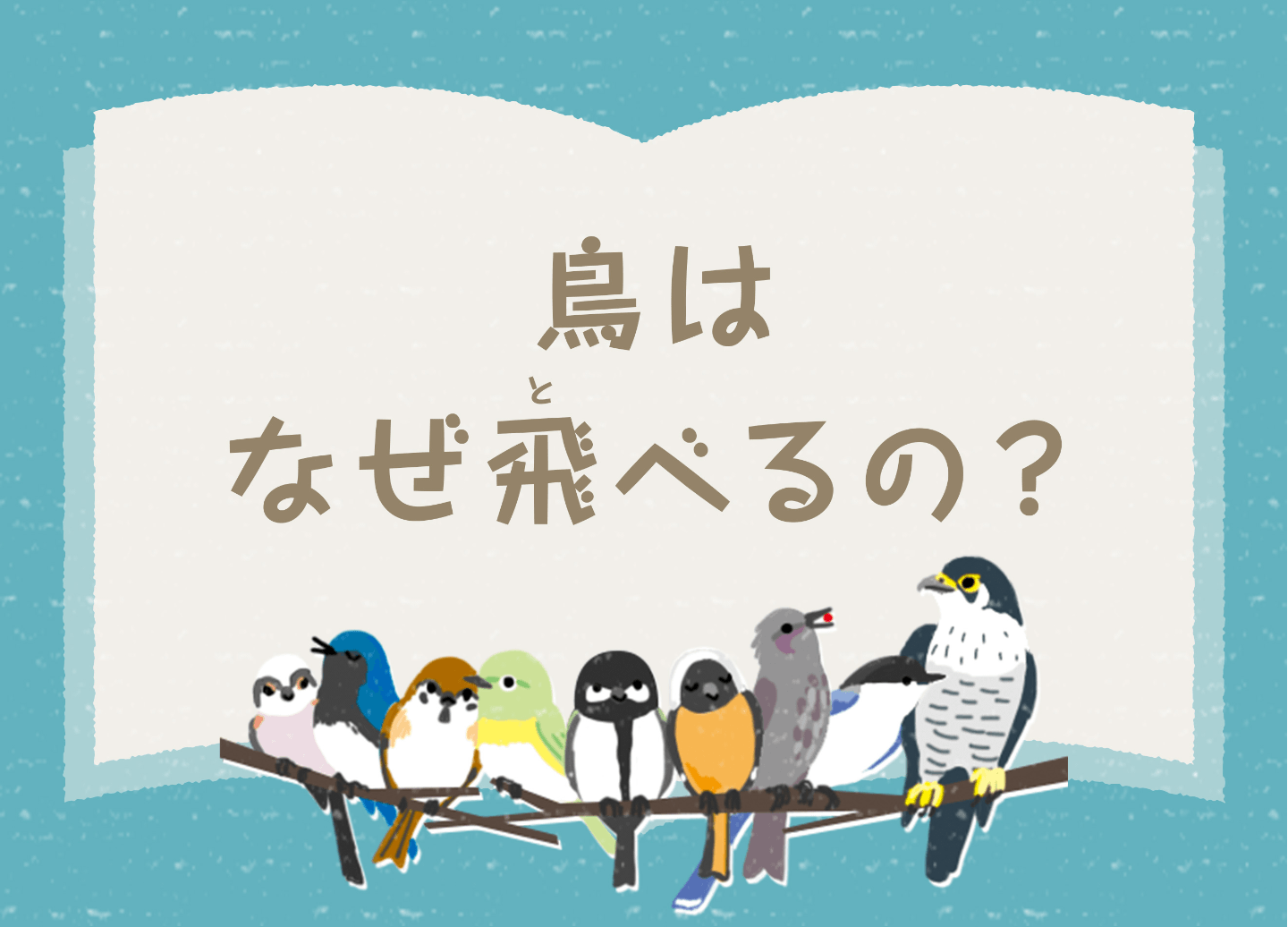
鳥のように空を
チャレンジ1
鳥のつばさのヒミツを見てみよう
鳥のつばさには、飛ぶための羽根である「
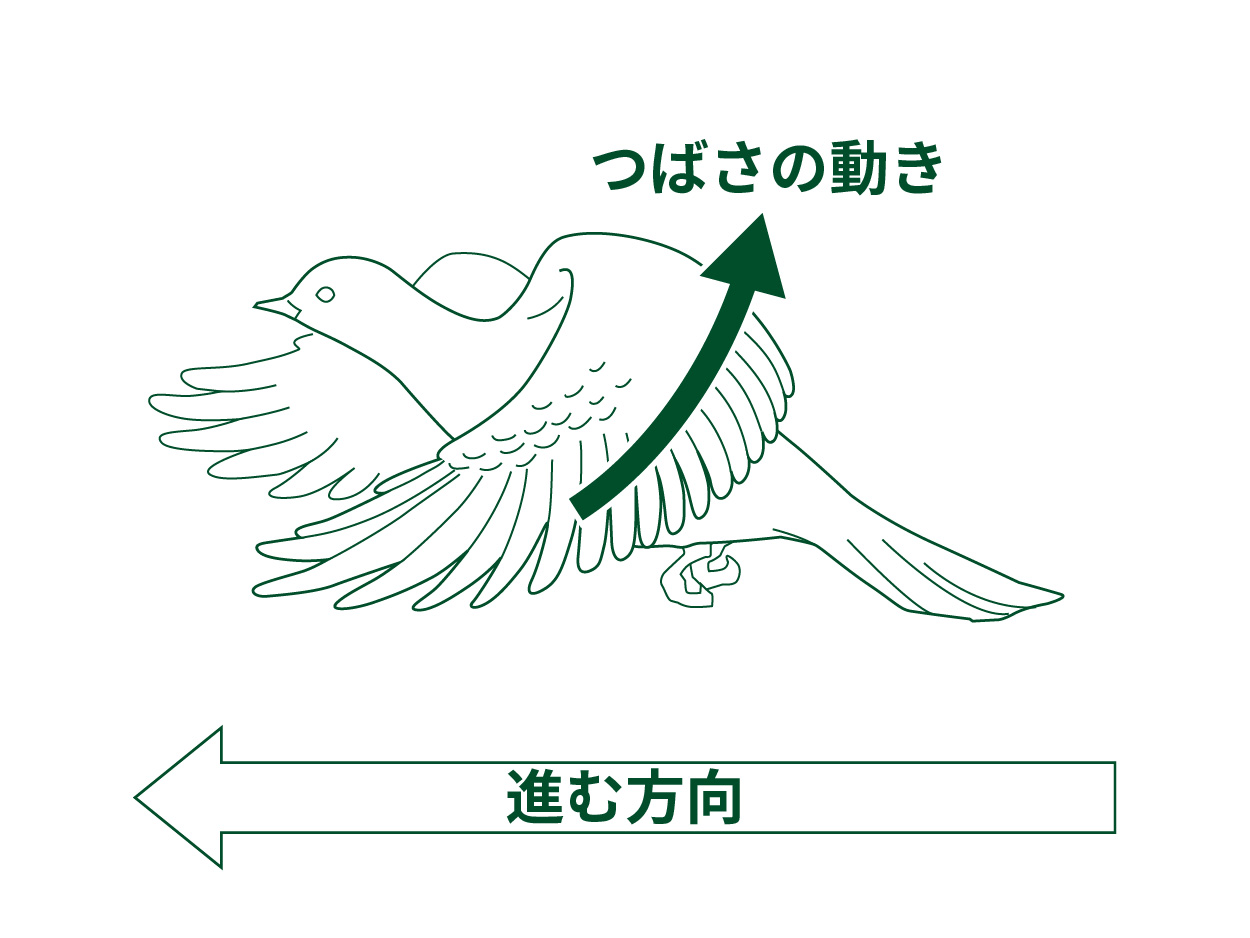
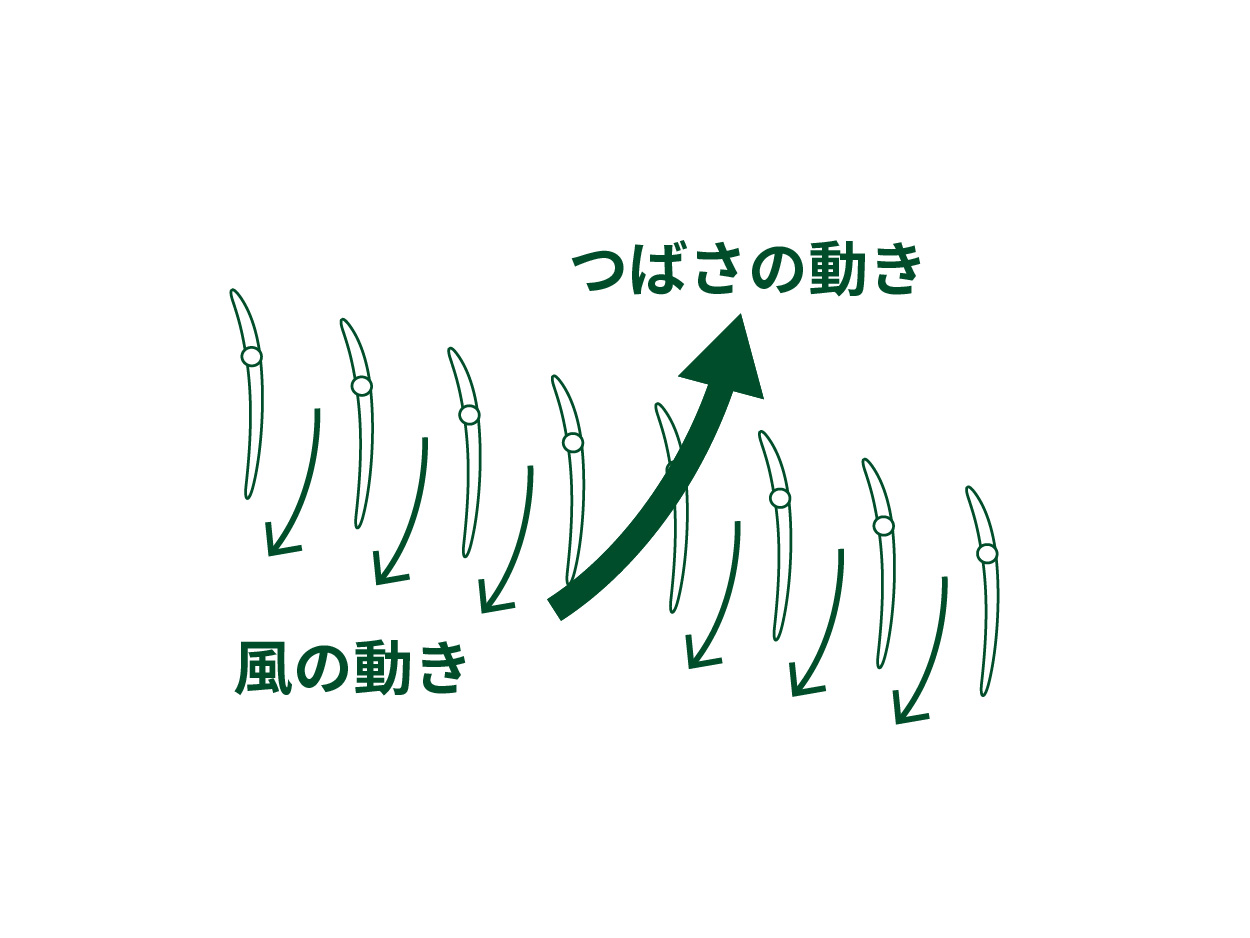
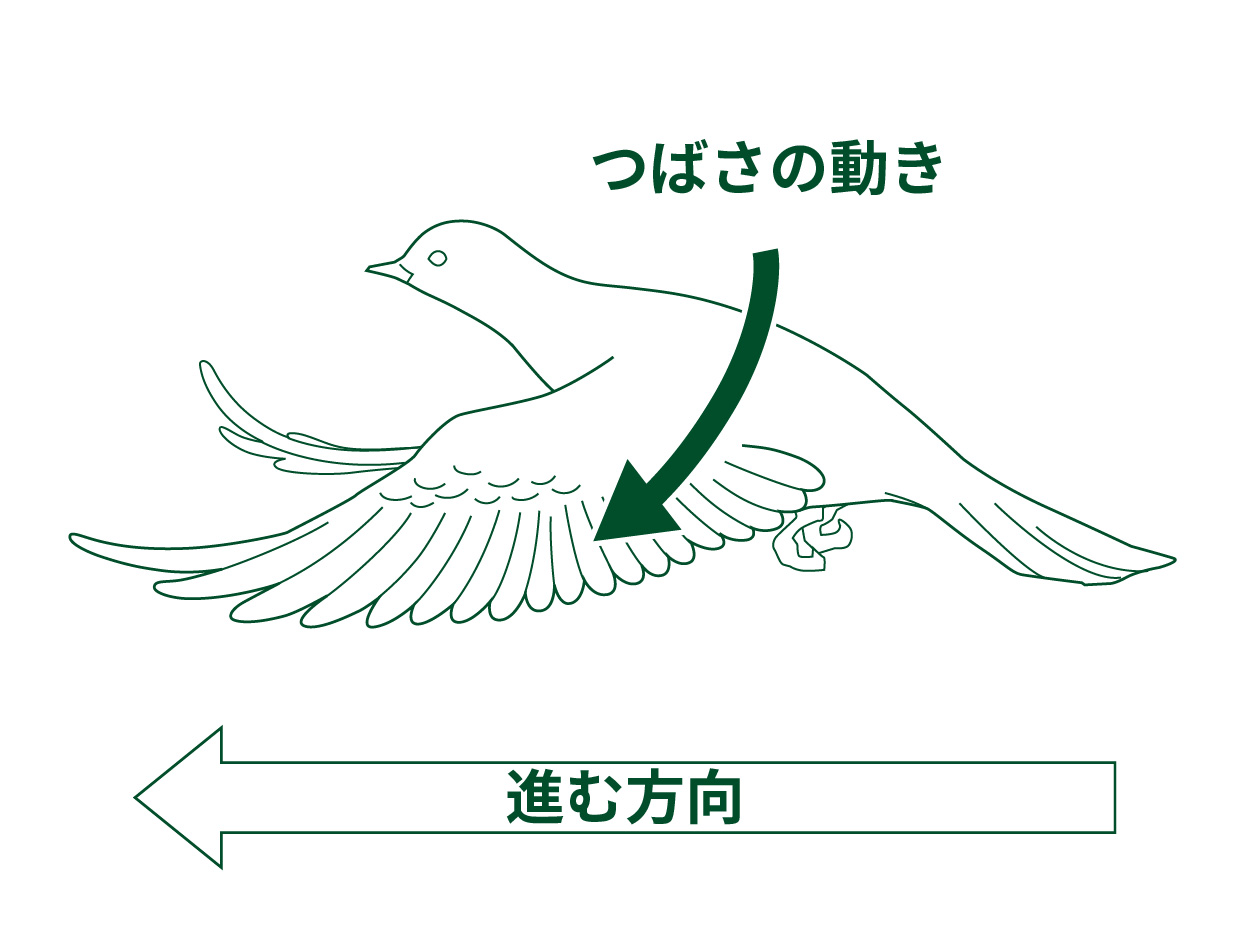
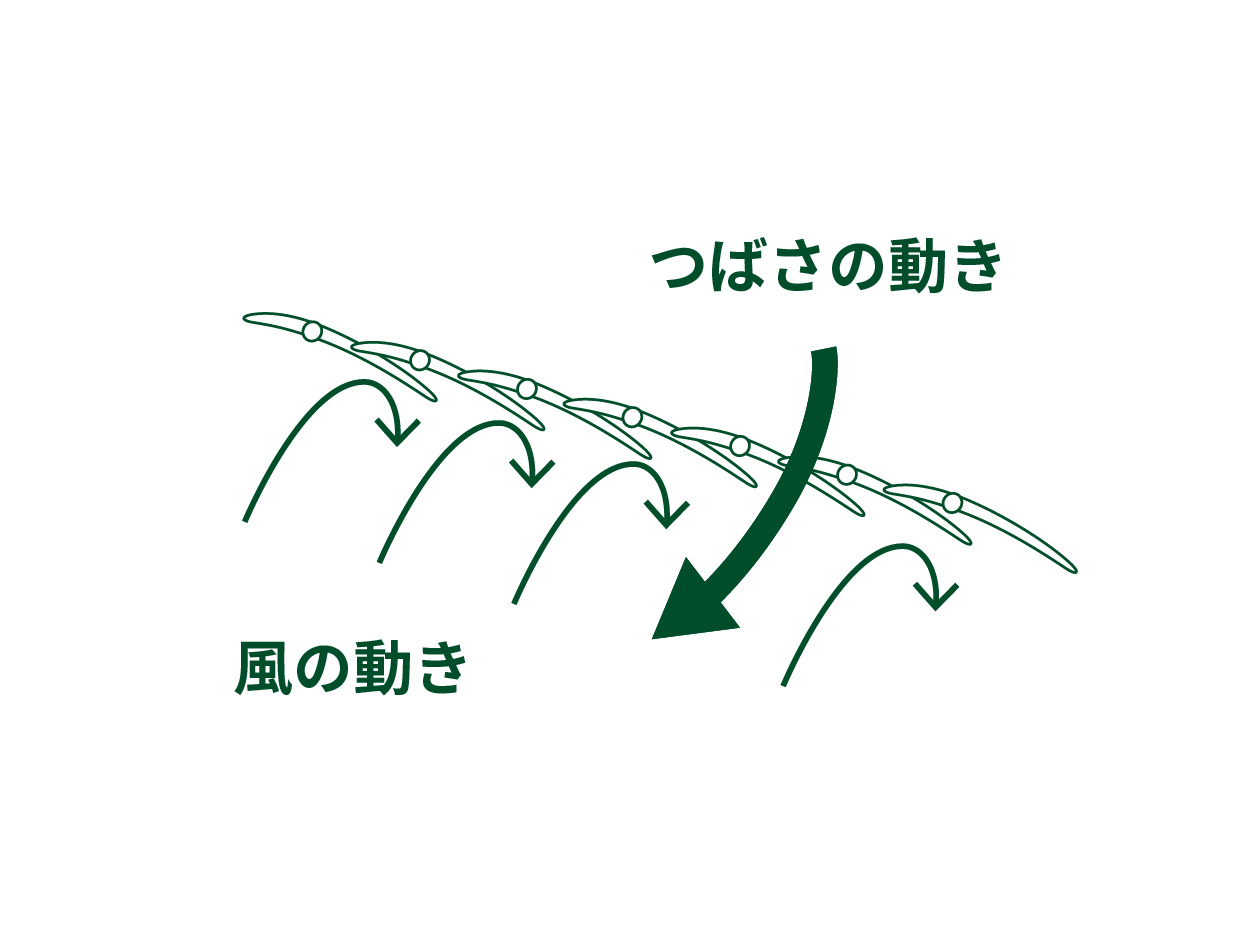
Q. つばさを上げたりおろしたりすると、どうして前に進むの?
鳥のつばさには、前に進むための「
初列風切を見つけたら、
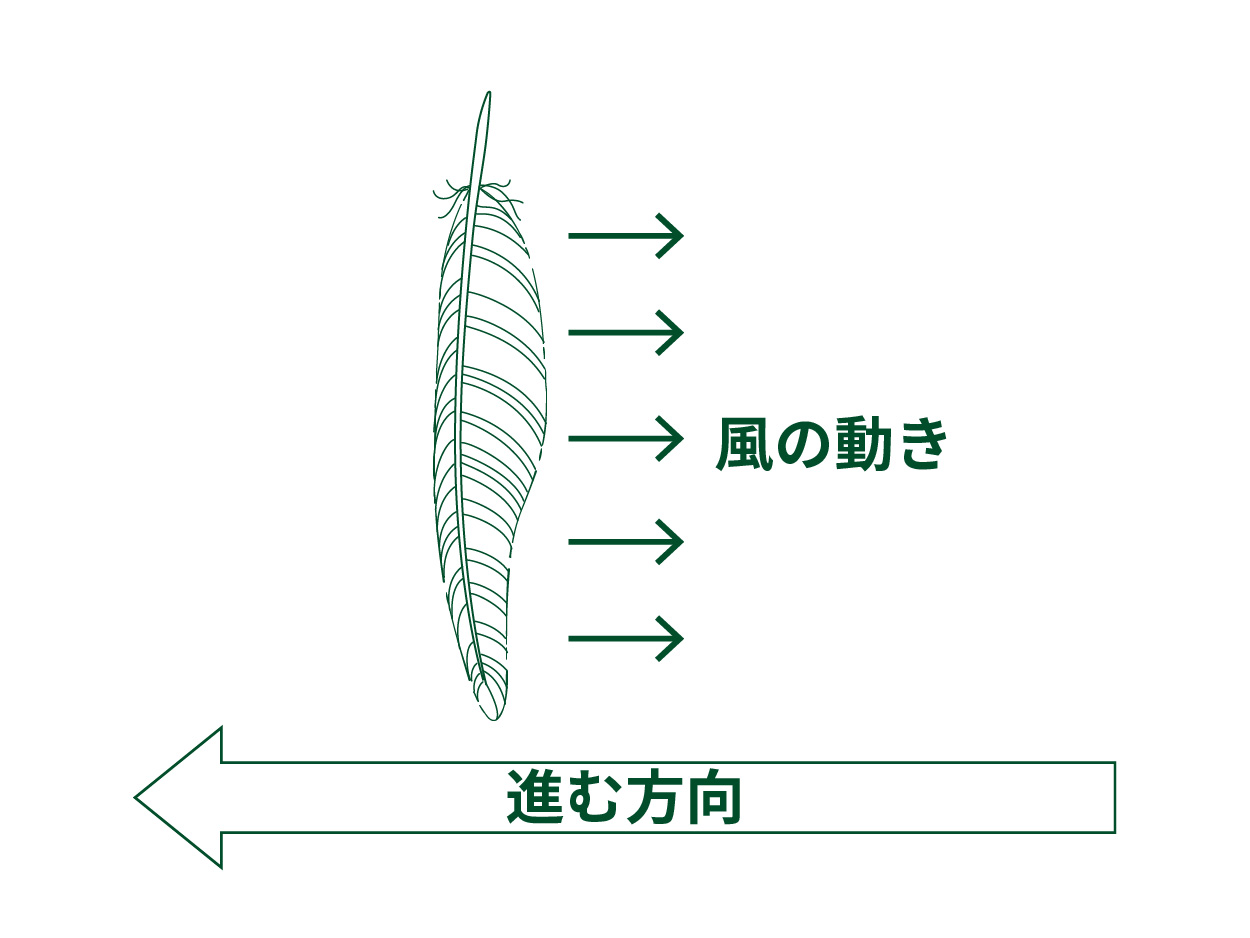
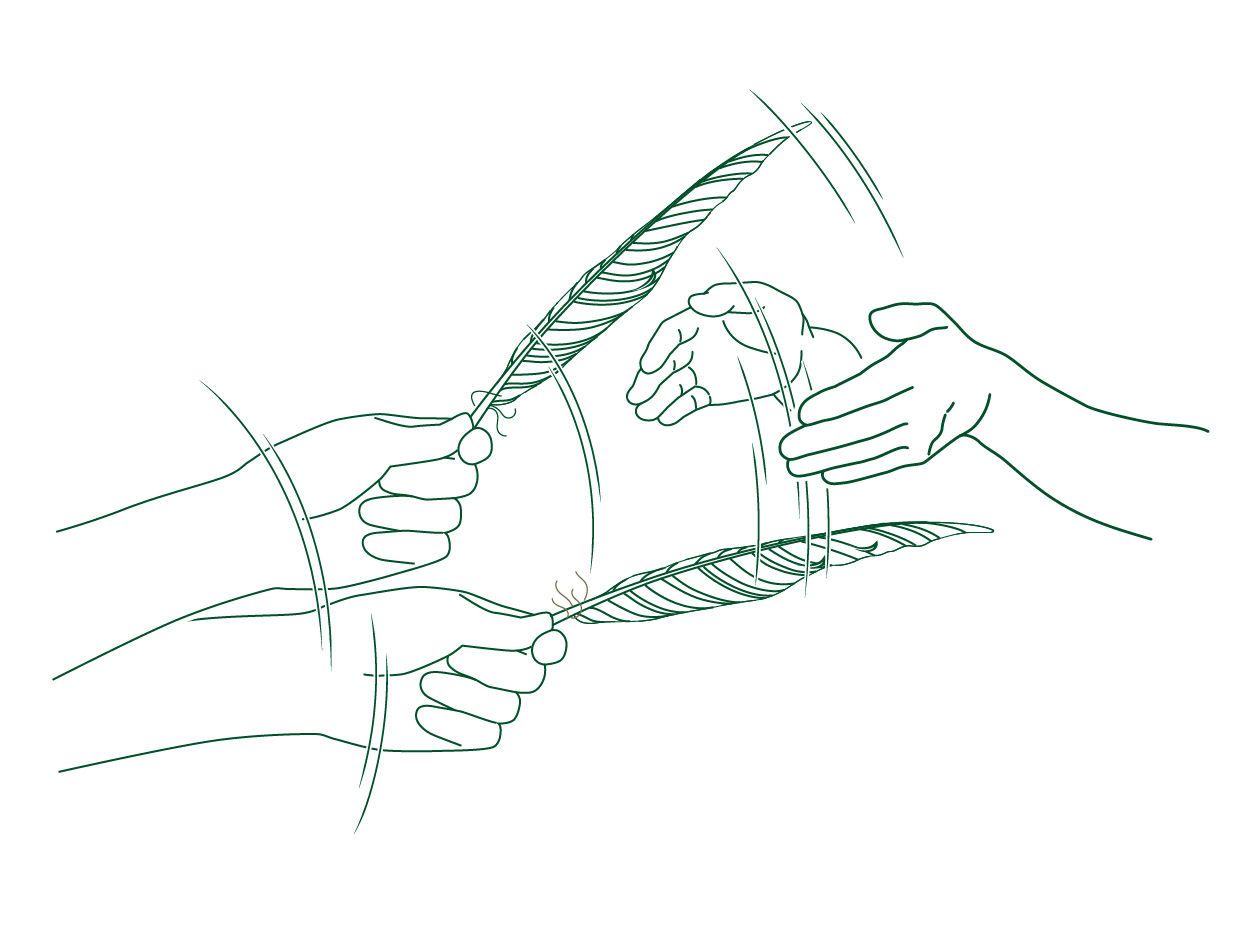
Q. どうやって羽根をお手入れするの?
鳥は、
よく見られるのは「
ヒバリやニワトリなどは、水浴びではなく「すな浴び」をします。つばさや
水浴びの様子
チャレンジ2
いろいろな羽根のはたらきを知ろう
飛ぶための羽根である「風切羽」にはいくつかの
鳥のつばさの先には、前に進むための「初列風切」が10
次列風切より内側には「
鳥がつばさを広げると大きく見えるのは、これら20枚ほどの風切羽が大きく広がるから。つばさをたたむと、風切羽は重なりあい、小さくセットされます。


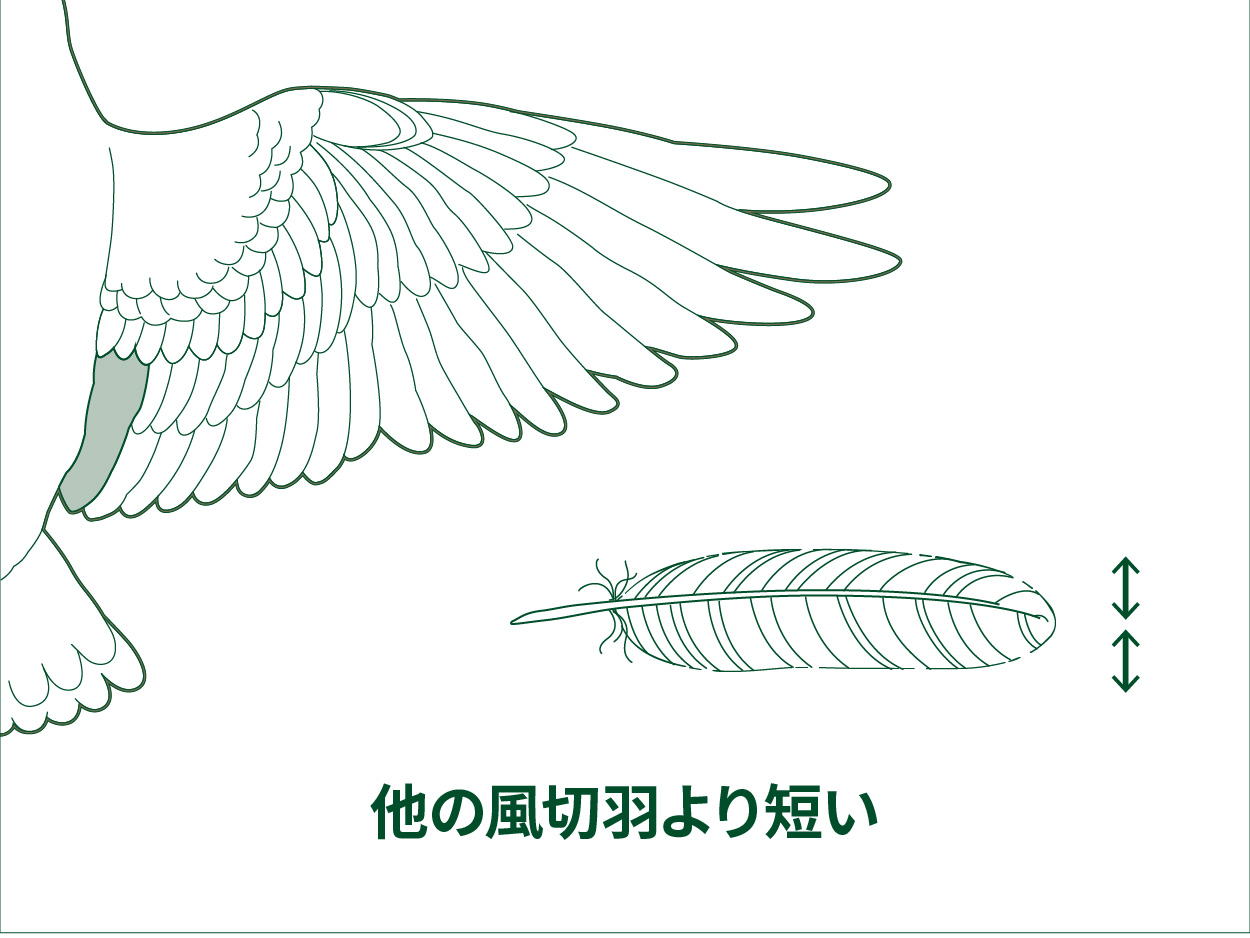
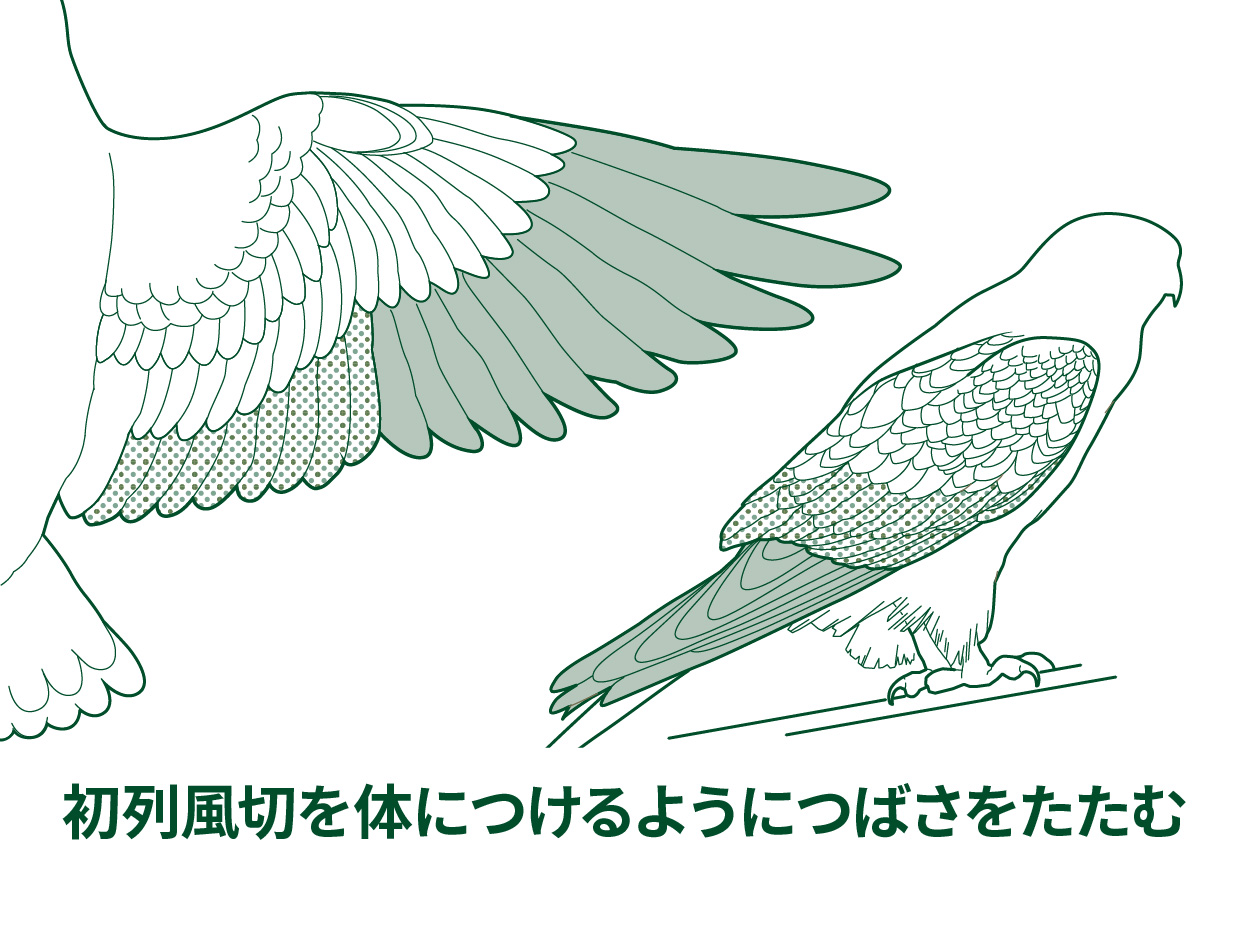
Q. 飛んでいるときのブレーキや方向転換(てんかん)はどうするの?
空中でブレーキをかけるときや方向を変えるときには、尾羽を使います。尾羽はだいたい12枚あって、次列風切に

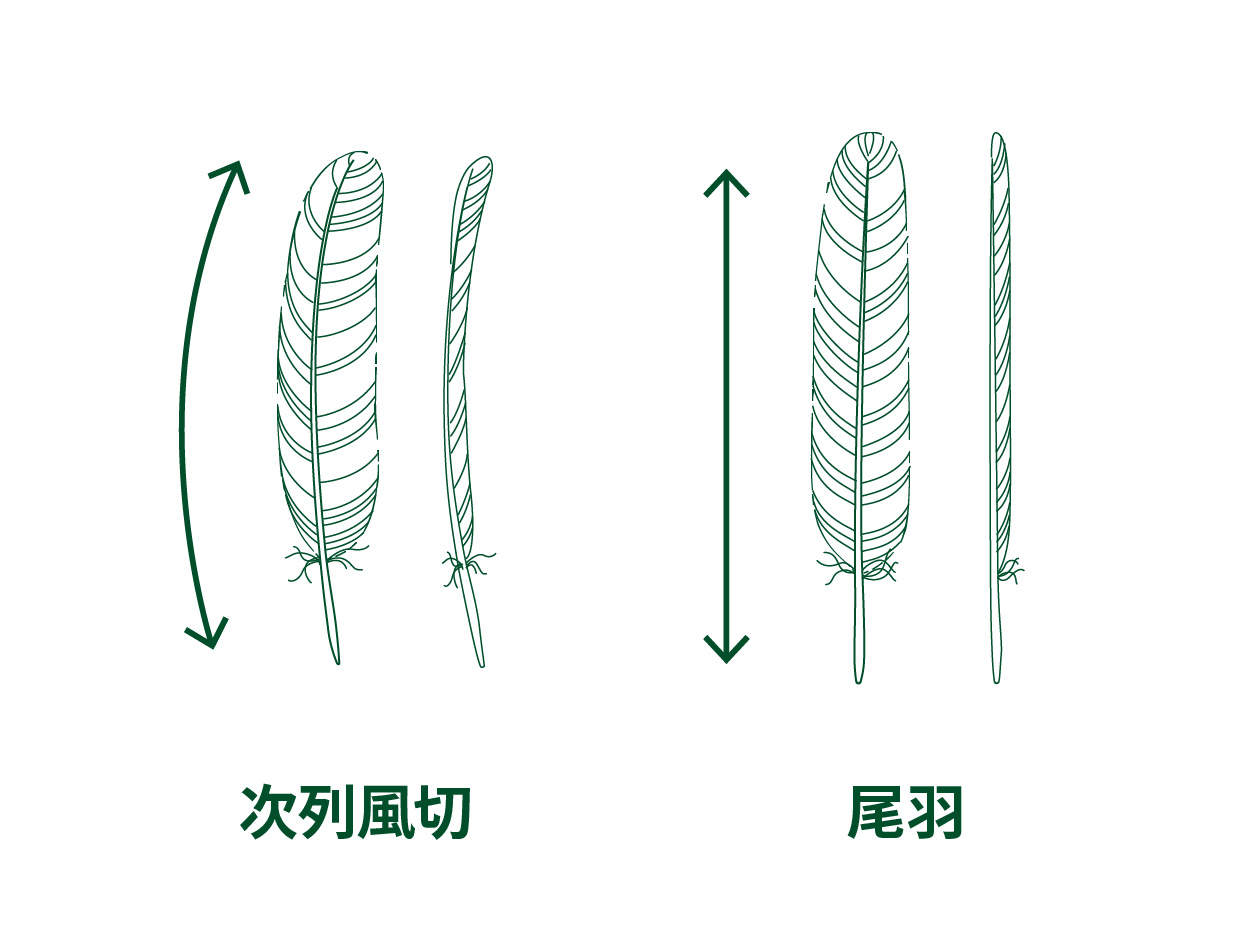
チャレンジ3
鳥の体のヒミツもみてみよう
もしみんなが空を飛びたいと思って、風切羽を身につけたとしても、
まずは、
また、体は軽くできていて、スズメより小さいメジロでは10グラムほど(はがき数枚くらい)しかありません。鳥の
体全体のうちの胸の筋肉と骨の重さの割合 (例 )
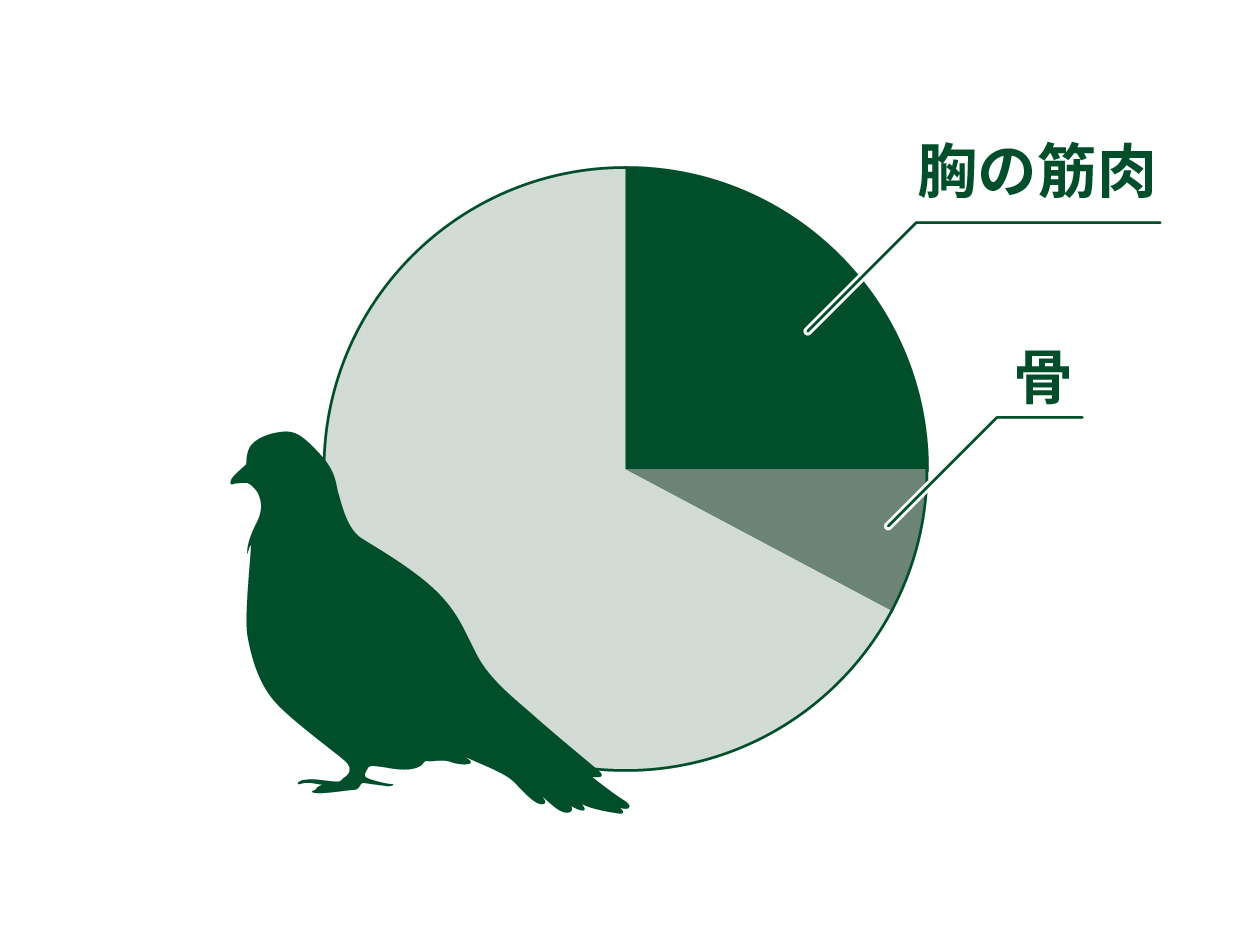
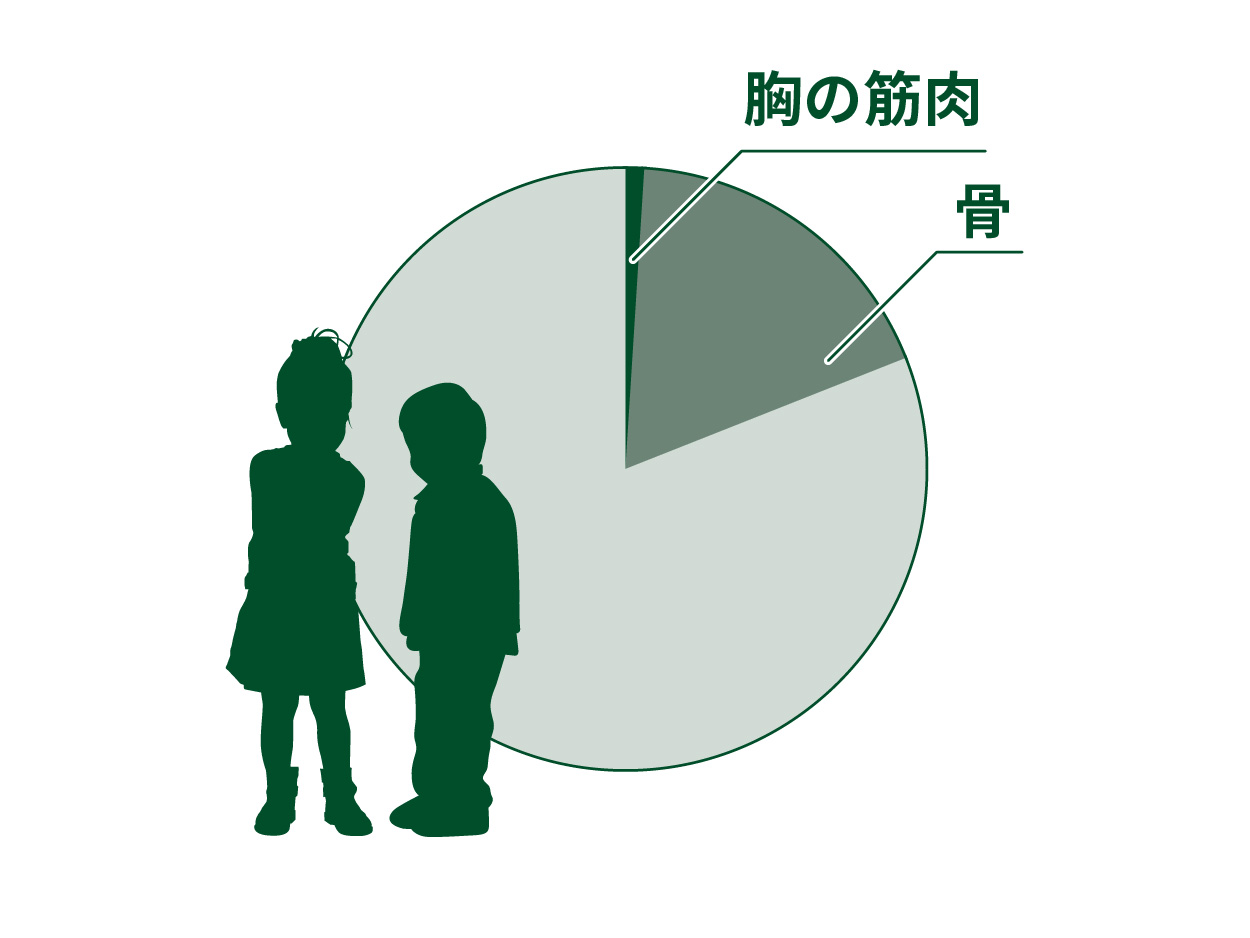
Q. 鳥はどうして同じ向きでとまるの?
理由は、鳥の羽根がすべて同じ方向に生えているから。鳥の羽根は「
流線形は

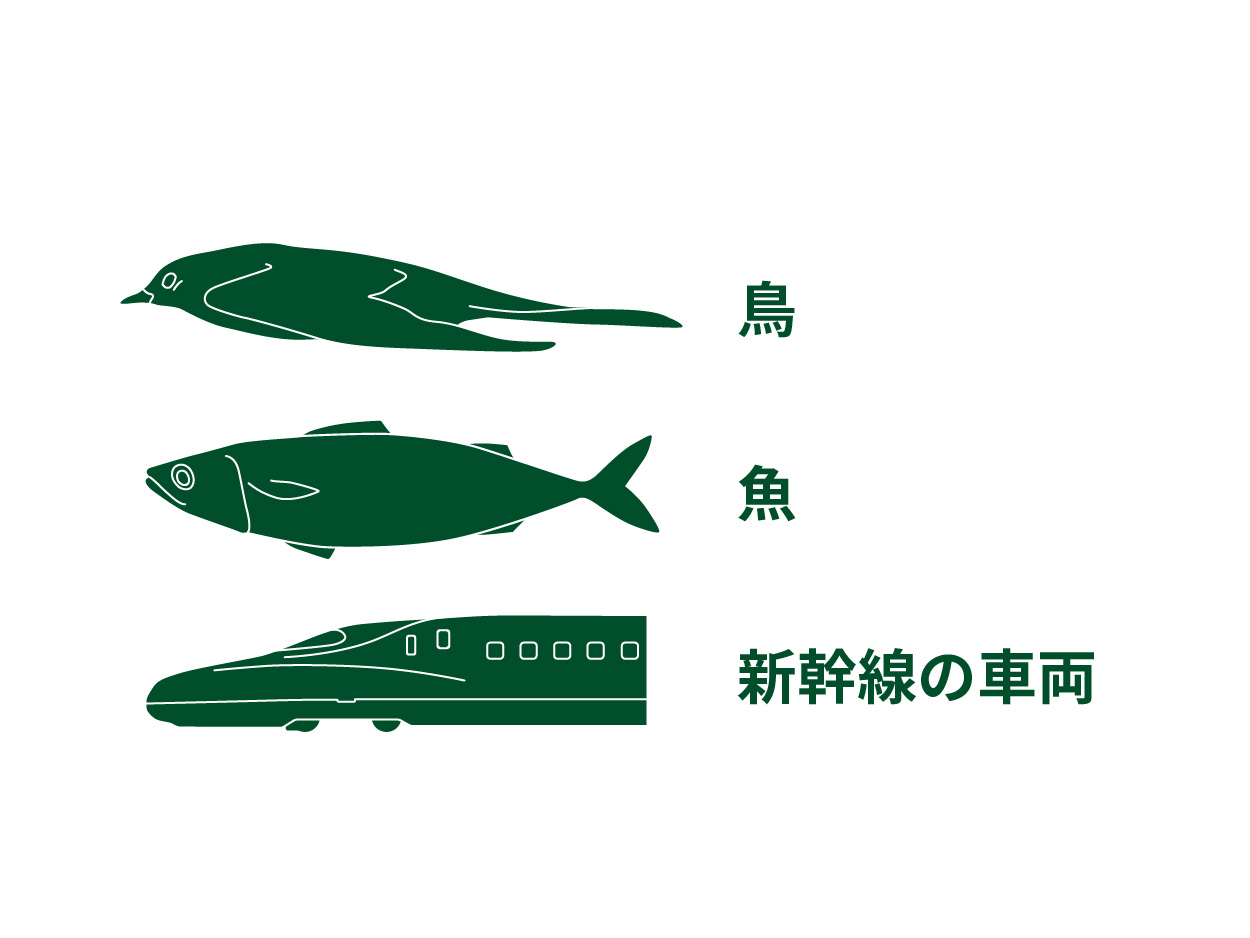
チャレンジ4
いろいろな飛び方をさがしてみよう
鳥たちは、つばさを上下に動かし、はばたくことで、進み、浮かび、飛んでいることがわかりましたね。飛んでいる鳥を見ると、はばたき方、飛び方にもいろいろあることに気づくはずです。
ハトは、はばたきながらまっすぐ飛びますが、ヒヨドリやセキレイのように、はばたいたり、休んだりをくり返しながら、波をえがくように飛ぶ鳥もいます。
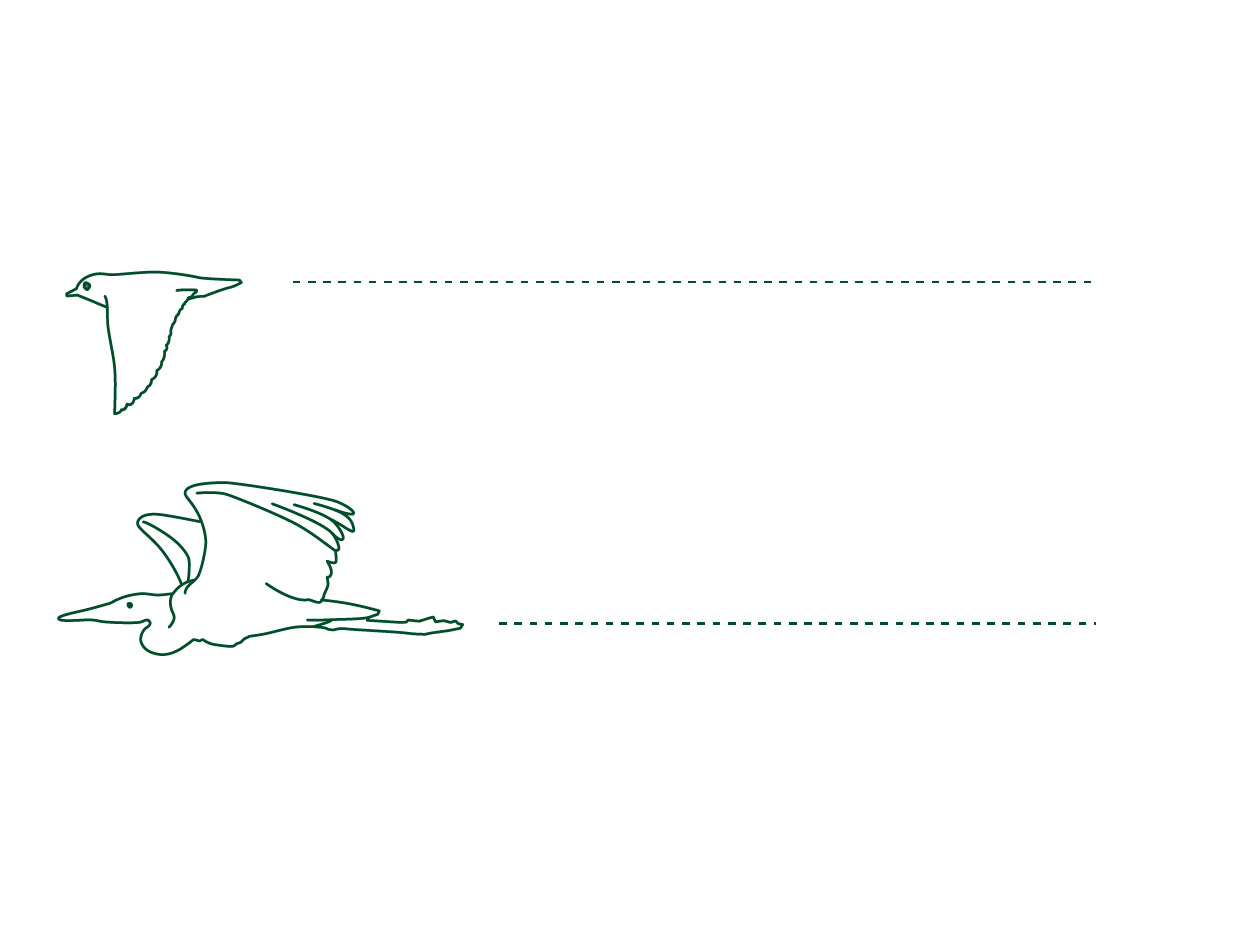
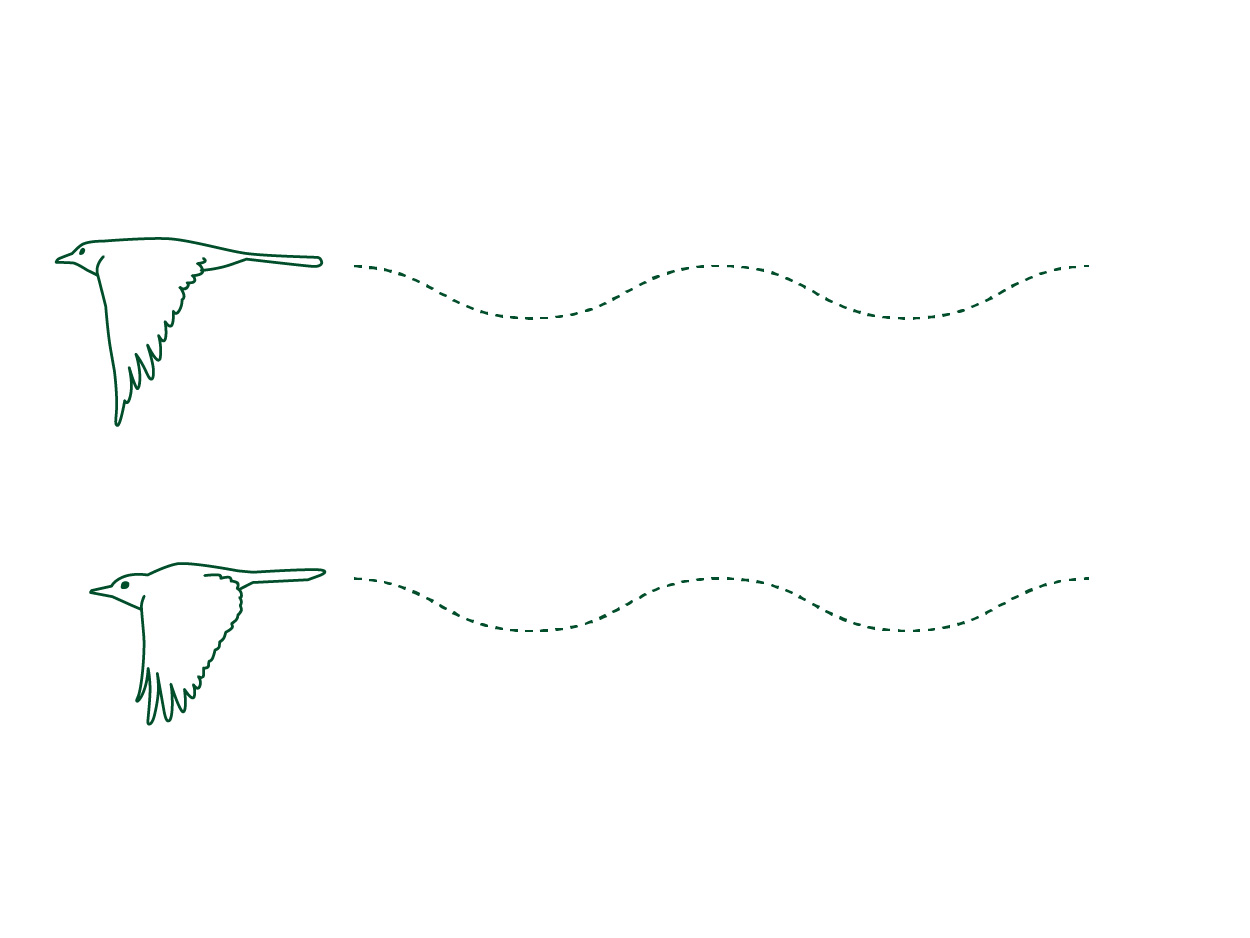
チョウゲンボウがえものをねらうときなど、前にも上にも進まず、空中にとどまる飛び方をします。これは「ホバリング」とよばれます。ヘリコプターが空中でとまっているときの飛び方もホバリングといいますね。
少しはばたいたあと、つばさを広げたまま、まっすぐ飛んでいく「
また、つばさを広げた滑空の


まとめ
鳥が空を飛べるヒミツがわかったかな?
自由に空を飛ぶために、鳥の体にはいろいろな
身近な鳥をよく観察すると、飛び方のちがいに気づいたり、つばさをお手入れする様子を見たりすることができるよ。みんなもワークシートをもって鳥をさがしに行こう!
解説者紹介
日本野鳥の会 参与(元主席研究員)
安西 英明
1956年東京都生まれ。
1981年日本野鳥の会が日本で初めてバードサンクチュアリに指定した「ウトナイ湖サンクチュアリ」(北海道)にチーフレンジャーとして赴任する。
現在は同会の参与として、野鳥や自然観察、環境教育などをテーマに講演、ツアー講師などで全国や世界各地を巡る。解説を担当した野鳥図鑑は45万部以上発行。