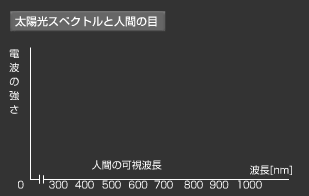「光」という言葉からはどんな光をイメージしますか。
誰しもが最初に思い浮かべるのが太陽の光でしょう。太陽は、常に光を発しています。
太陽から地球には、常時、光が届けられています。これは、言い方を変えれば「光のかたちで電磁波エネルギーがもたらされている」ということです。
太陽が放射する電磁波は、波長2ナノメートルのX線から波長10メートルの電波までと広範囲で、地表で最も強い強度となるのは、波長500ナノメートル前後の「可視光」です。
地球が太陽から受け取るエネルギーは「太陽定数」と呼ばれますが、これは1cm2あたり1分間に約2カロリーです。1m2あたりでは1.4キロワットに相当し、電気ストーブ1台分に相当します。大気の吸収などがあるため、地表ではこの数値より小さくなりますが、いずれにしても太陽が地球にとって大きなエネルギー源であることには違いはありません。
太陽は、半径69万6000kmの天体です。体積は地球の130万倍、重さは33万倍と、地球と比較すると大きな星ですが、銀河系のなかではごく普通の大きさです。その表面温度は6000度、中心温度は1500万度。この太陽は、どのようにして誕生したのでしょう。太陽の誕生は約50億年前といわれています。その頃、銀河系で巨大な星の寿命がつき、「超新星爆発」が発生しました。
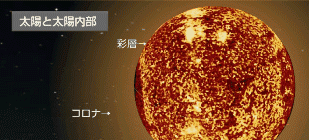
このような爆発が起きると、その衝撃波は周囲のガスを圧縮、ガスが冷えるにつれて水素原子や分子、ちりが集まった雲ができます。その雲は、みずからの重力によって長時間かけて収縮、内部は高密度、高温になります。そして、中心部が十分に高温(約1000万度)となると、水素と水素が結合してヘリウムとなる「核融合」が発生。大量のエネルギーを発生しながら輝きだすのです。このように、太陽のようにみずから輝く星(恒星)は巨大なガスの固まりで、内部では核融合反応が起こっているのです。
太陽の中心部では、毎秒6億5000万トンの水素が核融合反応してヘリウムに変化していると考えられています。核融合の際に発生するエネルギーは熱エネルギーとなり、中心部を高温に保ちつつ、太陽表面に伝わります。
地球が、太陽から受けているエネルギーの量は、100万キロワットの発電所2億基分といいます。しかしそれも、太陽全体が放出するエネルギーの20億分の1にすぎないというのですから、太陽における核融合の規模はばく大です。
太陽表面に伝わった熱エネルギーは、太陽表面でガス渦を作り出します。
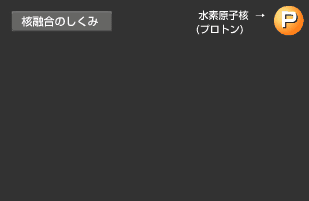
渦の対流によって強力な磁場ができることがあります。磁場が集中すると、「黒点」や「フレア」と呼ばれる爆発現象が起きます。
さて、太陽から地球に来る光の色は、何色に見えるでしょうか。太陽光を分解すると、横図のようなスペクトルとなります。波長約500ナノメートル前後の光をよく放出していて、太陽が「黄色」に見える理由がよくわかります。また、「太陽表面の温度は6000度」と前に説明しましたが、このスペクトルは、温度が6000度の物体から放たれる光のスペクトルと一致します。だから、太陽の表面温度は6000度とされているのです。このように、熱せられた物体が放出する電磁波のスペクトルは、物体の温度を調べるのに使われています。
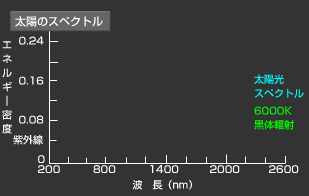
例えば、おおいぬ座のシリウスは青白い一等星で、表面温度が10000度を超える高温の星であることがわかります。
太陽の色は「真っ赤」ではなく、正確には「黄色」であることがわかったでしょうか。人間の目が感じる光を「可視光」といいますが、この可視光は、波長400~700ナノメートル前後の光です。しかも、もっとも感度がよいのが500ナノメートル前後だといわれています。これは、人間の目が、太陽光のスペクトルに適応するように進化してきたからだと考えられています。太陽がもっと高温の星であれば、可視光の範囲も違ったはずですが、当然ながらその場合は、現在の地球環境があるかどうか、人間ほかの地球生物が誕生できたかどうかも疑わしくなります。