環境・社会分野における重点課題(マテリアリティ)
マテリアリティについて
2022年、キヤノンは、改訂された国際ガイドラインGRIスタンダード2021をもとに、自社の活動が環境・社会に及ぼす正負ならびに潜在・顕在のインパクトの観点から環境・社会における重点課題(マテリアリティ)を検討し、経営陣との協議を経て、下記の項目をマテリアリティとして特定しました。特定にあたっては、次の4つのステップを経ました。
〔ステップ1〕
各種国際的な枠組み、サステナビリティ調査など各種指標、ステークホルダーと直接の対話などを通じ社会課題を把握
〔ステップ2〕
自社の事業活動や中長期経営計画に沿った活動が環境や社会に与えるインパクトを把握
〔ステップ3〕
インパクトの重要性を評価
〔ステップ4〕
社外のサステナビリティ専門家との対話を通じて評価結果の選定項目や優先順位を検証
キヤノンは毎年、世界各国・地域におけるサステナビリティに関する動向調査や関連法規制の分析を実施し、マテリアリティの妥当性を確認しています。
また、2024年は欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)や国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)などで定められたサステナビリティ開示基準への対応を視野に、マテリアリティの検討を始めました。
特定した重点課題(マテリアリティ)への目標と結果
- 環境分野
- 社会分野
環境分野
★:達成または良好 ☆:一部達成
| 重点課題 (マテリアリティ) |
重要度 | めざすもの | 主な目標 | 2024年の成果/実績 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
気候変動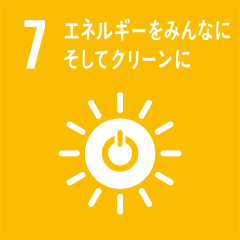
 |
最重要 | 2050年に製品ライフサイクルを通じたGHG排出量ネットゼロの達成 | SBTiの基準に即し、2030年にスコープ1※、2※のGHG排出量を2022年比で42%削減、スコープ3※(カテゴリー1、11)のGHG排出量を2022年比で25%削減 | 2022年比でスコープ1、2のGHG排出量12.8%削減、スコープ3(カテゴリー1、11)のGHG排出量17.7%削減 | ★ |
| ライフサイクルCO2製品1台当たりの改善指数:年平均3%改善 2030年に2008年比50%改善 |
年平均3.76%改善(2008~2024年) | ★ | |||
資源循環  |
最重要 |
|
原単位当たりの廃棄物総排出量:1%改善 | 2.2%改善 | ★ |
| プリンティング製品の資源循環率 2025年:20%、2030年:50% |
約17% | ☆ | |||
化学物質  |
最重要 | 製品や生産で使用する化学物質の徹底管理 | 原単位当たりの管理化学物質排出量:1%改善 | 0.9%悪化 | 洗浄工程による品質改善にともなう使用量増加などの要因による効率悪化で目標未達。工程に適した排出量管理の徹底で目標達成をめざす |
| 当該化学物質の使用禁止期限の1年前に製品への含有禁止 | 含有ゼロ | ★ | |||
生物多様性   |
重要 |
|
事業活動を行う地域における環境影響の把握、動植物の生息/生育空間の保全 |
|
★ |
| 原単位当たりの水資源使用量:1%改善 | 0.6%改善 | 水使用量の多い製品品種の製造比率増などの要因による効率悪化で目標未達。工程に適した使用量管理の徹底で目標達成をめざす |
社会分野
★:達成または良好 ☆:一部達成
| 重点課題 (マテリアリティ) |
重要度 | めざすもの | 主な目標 | 2024年の成果/実績 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
人権と労働 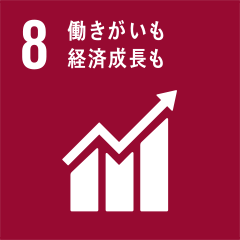   |
最重要 | 事業活動におけるすべてのステークホルダーの人権を尊重 | 人権デュー・デリジェンスの実施によりリスク低減 |
|
★ |
| 従業員一人ひとりの個性、能力を最大限に生かし、かつ多様性を相互に認め合いそれぞれが活躍できる環境 | キヤノン(株):女性管理職比率2025年末までに2011年比の3倍以上 | キヤノン(株)女性管理職比率:4.2% | ★ | ||
| キヤノン(株):男性の育児休業取得率2025年末までに50%以上 | キヤノン(株)男性の育児休業取得率:64.6% | ★ | |||
| 従業員にとって安心・安全な職場環境 | キヤノン(株)および国内グループ会社:機械装置起因の挟まれ・巻き込まれ災害(0件) | キヤノン(株)および国内グループ会社:機械装置起因の挟まれ・巻き込まれ災害(2件) | 災害発生により未達成だが、再発防止策の実施および引き続きリスクアセスメントを実施し、目標達成をめざす | ||
| キヤノン(株)および国内グループ会社:有害性の高い化学物質起因の災害(0件) | キヤノン(株)および国内グループ会社:有害性の高い化学物質起因の災害(0件) | ★ | |||
社会文化支援活動         |
重要 | よき企業市民として、よりよい社会の実現に貢献 | キヤノンのもつ「高度な技術力」「グローバルな事業展開」「専門性のある多様な人材」を有効に活用し、国際社会と地域社会のなかで社会文化支援活動を推進 |
|
★ |
- ※ スコープ1:直接排出(都市ガス、LPG、軽油、灯油、非エネルギー系温室効果ガスなど)、スコープ2:間接排出(電気、蒸気など)、スコープ3:サプライチェーンでの排出(購入した物品・サービス、輸送・流通、販売した製品の使用など)
| 重点課題(マテリアリティ)(P10-11) (1.3MB) |
