白熱灯や蛍光灯にかわる人工光源として注目されているのがLEDです。
手軽で身近になりつつあるLEDを見てみましょう。
すでにLED(発光ダイオード)は、身近に使われています。TVやパソコンなどの電化製品の片隅で小さく光る赤や緑色の動作表示ランプ、あれがLEDです。LEDは、電流をストレートに光に変換するためエネルギー効率のよい照明になるのですが、これまでは技術的に赤や緑のLEDしか作れなかったため、使用には限度がありました。90年代になって青色のLEDが開発されてカラー表示が可能となり、現在、急速に用途が広がっています。ビルの壁面などに設置されている街頭ディスプレイは、LED表示によるものです。カラー複写機やスキャナーの光学的読み取り部にも応用されています。
LEDの仕組みを理解するには、まず「太陽電池」のように光をあてると電流が得られる仕組みを理解しましょう。よく耳にする「半導体」は、コンピューターをはじめとする電子回路の材料で「シリコン(Si)」が多く使われています。半導体には、電子が余っている状態の「n型」シリコンと、電子が不足し、その不足したところが「正孔」といわれる“穴”となる「p型」シリコンがあります。このふたつを接合したものが「pn接合ダイオード」と呼ばれるものです。このpn接合の部分に光をあてるとp型の部分がプラス極、n型の部分がマイナス極となり、p型、n型の部分にそれぞれ電極を付け、外部に電線をつなぐと、電流を取り出すことができます。これは太陽電池の原理でもあります。
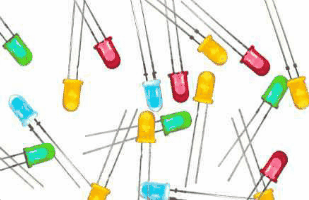
pn接合ダイオードでは、どんなことが起こっているのでしょう。太陽光などの光がシリコンにあたると、そのなかでは電子と正孔が発生します。p型シリコンとn型シリコンの部分を外部につないでやると、電子が余分なp型シリコンのなかの電子はn型シリコンのほうへ、逆に正孔が多いn型シリコンの正孔はp型シリコンのほうへと移動していきます。したがって、n型シリコンに付いている電極からは電線を伝わって過剰の電子が流れ出し、p型シリコン側の電極へと向かい、電流が生じるのです。電流の流れは電子の流れる方向の逆方向と定義されますので、p型シリコンをプラス極、n型シリコンをマイナス極とする電流が得られます。
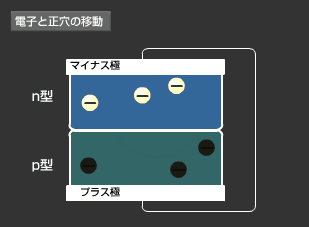
太陽電池のように、性質の違うシリコンの組み合わせに光をあてると電流を得られるのならば、その逆もあるはずです。つまり、外部から逆方向に電流を与えたらpn接合部から光が出てくるかもしれません。実はその通りの現象が起こり、n型シリコン側をマイナス極、p型シリコン側をプラス極にして電流を流してやると光が発生します。これが「発光ダイオード」(LED)です。ただし、このままでは発光効率が悪く、実用化できません。ガリウム・ヒ素、ガリウム・リン、ガリウム・リン・ヒ素といった化合物を半導体材料にしたpn接合を作り、実用化しています。
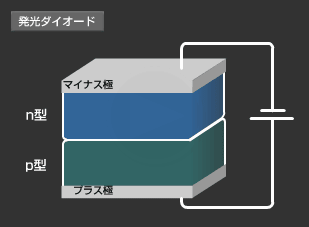
pn接合を利用してできるのが、「半導体レーザー」です。半導体の中にpn接合を作り、n型に流れ込む電子とp型の正孔とにより「反転分布」を実現させるのです。pn接合面に直角な形の鏡、この場合は使う半導体の結晶の「へき開面」(結晶のきれいな割れ方の面)を半導体の両面にうまく作れば、そのへき開面間を光が往復して強まり、位相と方向がそろったレーザー光を取り出すことができます。この半導体レーザーは、「レーザー・ダイオード」とも呼ばれます。大きさはわずか約300マイクロメートル角、厚さは約80マイクロメートル。
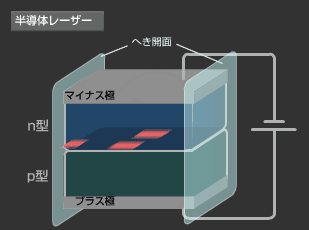
CDやレーザープリンター用に、ガリウム・アルミニウム・ヒ素を利用した700ナノメートルの波長のレーザー光を出すレーザー・ダイオードが量産されています。
