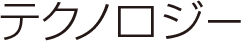人間の眼を超える技術
CMOSセンサーの
開発秘話
キヤノンはこれまでカメラのキーデバイスとして、CMOSセンサーを内製で開発・生産し続けてきた。IoT時代には、最先端イメージセンサーとして、さまざまな用途での展開が期待され、市場規模の拡大が見込まれている中で、キヤノンの技術者は一丸となり、これまでにない世界最高レベルのCMOSセンサーを生み出した。
キヤノンのCMOSセンサーの技術について映像でご紹介します
今回の「語る」開発者

領木 達也(りょうき たつや)
- 担当:デバイス設計

鳥居 慶大(とりい けいた)
- 担当:プロセス開発

赤堀 博男(あかぼり ひろお)
- 担当:デバイス設計

木戸 滋(きど しげる)
- 担当:半導体製造技術

大貫 裕介(おおぬき ゆうすけ)
- 担当:デバイス要素開発

高田 健司(たかた けんじ)
- 担当:デバイス販売推進


18km先の航空機の文字が
見える!
驚異の2.5億画素センサー
2010年にキヤノンは1.2億画素のCMOSセンサーを実現して注目を集めた。次に開発チームに与えられたミッションは、倍の性能、2.5億画素を持つ超多画素センサーの開発だった。画素の微細化、周辺回路の高速化という困難な課題をチームはどうクリアしたのか?
領木 達也(りょうき たつや)
担当:デバイス設計
2004年に入社し、半導体材料開発部門を経て、2007年よりセンサー開発を担当。
技術課題に対し、できない理由を考えるのではなく、どうすればできるかを考え、前向きに取り組むことをモットーに、日々仕事に従事している。
2.5億画素もあると18km先を飛んでいる航空機の機体に書かれた文字が読めるんですね。このCMOSセンサーは、どういうところから開発が始まったのでしょうか?
領木達也
2010年の時点ですでにキヤノンは1.2億画素のCMOSセンサーを実現していました。1.2億画素というのは、人間の視細胞数に相当します。さらにその倍の性能を実現し、圧倒的な優位性をアピールしようというチャレンジングなプロジェクトとして、2.5億画素のイメージセンサー開発がスタートしました。
高田健司
画素数を1.3億や1.4億に増やしても、すぐ他社にキャッチアップされてしまいますから、そこはどんと倍にして世界一を狙いました(笑)。
領木
単に多画素にするだけでなく、美しい画像を実現できるよう一つひとつの画素そのものの性能にもこだわりました。結構苦労もありましたが、目標としていた性能は達成できたと思います。
 撮影した映像(写真左)を電子ズームし、さらに画像処理技術を活用。人間の眼では認識することが難しい約18km先を飛行する機体文字の識別が可能に。(写真右)
撮影した映像(写真左)を電子ズームし、さらに画像処理技術を活用。人間の眼では認識することが難しい約18km先を飛行する機体文字の識別が可能に。(写真右)(EF800mm望遠レンズと電子ズームを用いた試作機での撮影)
2.5億画素という目標の難易度はかなり高かったのでしょうか?
領木
センサーのチップサイズに制約がある中で、その中に全ての要素を収めなければなりません。それを実現するためには、CMOSセンサーにおける画素構造を開発するデバイス設計と、製造工程を開発するプロセス開発、そして工場の3部門による密接な連携が不可欠です。
鳥居 慶大(とりい けいた)
担当:プロセス開発
2008年に入社以来、CMOSセンサーの製造プロセス技術開発に携わっている。
自分の専門外の仕事に対しても臆せず、分野・能力を広げるチャンスと捉えることを心がけている。
鳥居慶大
プロセス側のテーマは、大きく分けて2つありました。従来と同じ面積のチップの中に2倍も多い画素を詰め込むことになりますから、そのための微細化が1つ。もう1つは、小さくなった画素でいかにして光を取り込むか、です。
木戸滋
CMOSセンサーは多数の半導体から画素部を構成しているため、画素部を均一に製造する必要があります。そのため、取り込んだ光を全ての画素に対して均一に当てなければなりません。メモリーなど他の半導体に比べて、微細化と均一化を両立させる要求レベルが高いのです。そのため、工場での製造段階で歩留まりを上げることも難しくなります。
鳥居
例えば、これまで1ミクロンのゴミが入り込んだらアウトだったのが、微細化が進むと0.1ミクロンのゴミでも不良品になってしまうわけです。
画素が2.5億にもなると、扱うデータ量も倍増することになりますね。
領木
毎秒5コマ撮影するなら1秒間に12億5,000万画素分の信号を処理する必要がありますから、周辺回路を高速に動作させなければなりません。CMOSセンサーのプロセスというのは、電子回路を形成するためのプロセスと、画素を形成するためのプロセスの2つから構成されていて、この2つをマッチングさせるのに苦労しました。
どういう苦労がありましたか?
 2.5億画素CMOSセンサー(写真右)を搭載した試作カメラ(写真左)
2.5億画素CMOSセンサー(写真右)を搭載した試作カメラ(写真左)(EF35mm F1.4L USM」 装着時)
領木
回路については従来よりも低電圧で高速に動作する周辺回路用のプロセスを使うわけですが、同じ条件を画素用のプロセスに使うと画素の特性に悪影響を与えてしまうことがあるのです。開発の初期段階において、新しい高速回路用のプロセスでチップを作ってみると、画素の特性がまったく出ないことがありました。黒い画面を撮影しても、白く光る傷が無数に発生してしまっていたんです。
チップを実際に割って断面を観察し原因を探ったところ、周辺回路プロセスで適用している温度だと画素プロセスには不十分だということがわかりました。
大貫裕介
結果を受けて私たち画素担当のチームでシミュレーションを行い、どういう条件にすれば周辺回路と画素のプロセスを両立できるのか目星をつけて、回路設計やプロセスのチームに提案を行いました。
鳥居
設計、プロセス、工場が密接に連携していて担当者の顔が見えるのは、大きなメリットだと思います。


真っ暗闇が真昼に見える!
驚愕の超高感度センサー
2017年、元日の新聞に掲載されたキヤノンの広告には、色鮮やかな平等院鳳凰堂が掲載されていた。実はこの平等院鳳凰堂、真夜中に撮影されたものだったのである。真夜中でも真昼のような撮影を可能にする超高感度センサーを実現するため、開発者たちはどんな取り組みを行ったのか?
赤堀 博男(あかぼり ひろお)
担当:デバイス設計
1995年に入社し、回路設計、評価、生産技術に従事。
関連部門とコミュニケーションをとりながら、技術を幅広く捉えることで、より良い製品を作ることをめざしている。
元日の新聞に掲載された平等院鳳凰堂の写真はよくある風景写真かと思ったら、真夜中に撮影したものだったんですね。このセンサーの性能にも驚かされました。
 キヤノン初の超高感度多目的カメラ「ME20F-SH」
キヤノン初の超高感度多目的カメラ「ME20F-SH」
赤堀博男
キヤノンでは2013年に、動画専用35mmフルサイズの超高感度CMOSセンサーを開発しています。このセンサーでは、線香の光だけの暗い室内(照度0.05~0.01lux)での動画撮影を実現しました。
さらに完成度を上げ、0.0005lux以下でもカラー動画撮影を可能にしたセンサーを2015年に開発しており、それを搭載したキヤノン初の超高感度多目的カメラ「ME20F-SH」が発売されました。平等院鳳凰堂の広告にはこのカメラが使われています。
市販のデジタル一眼レフカメラに比べても、圧倒的な感度ですね。
 真夜中の平等院鳳凰堂の撮影
(上記ボタンのクリックで画像が切り替わります。)
真夜中の平等院鳳凰堂の撮影
(上記ボタンのクリックで画像が切り替わります。)
赤堀
キヤノンのデジタル一眼レフカメラの最上位機「EOS-1D X Mark Ⅱ」に比べて画素サイズは実に7.5倍以上です。ISO感度は一般的に3200程度が撮影の上限なのに対し、超高感度CMOSセンサーでは400万相当になります。
従来私たちの組織は、事業部からスペック・仕様を受けてそれに合わせたセンサーを開発するのが一般的でした。しかし、これからは自分たちで技術的なロードマップを考えて、新しいイメージセンサーを事業部に積極的に提案していこうということになりました。この超高感度センサーは、そのための第一歩ということになります。
そこで技術アピールをするのに、「ISO感度が1.××倍です」ではどうにもインパクトが弱い。そこでインパクトがあって、なおかつ自分たちの持っている技術やニーズとかみ合うように「デジタル一眼レフ最上位機を超えるISO感度の実現!」をスローガンに開発を進めました。
感度をアップさせるためにどのような工夫をされているのでしょうか?
 1画素内の構造
1画素内の構造
赤堀
CMOSセンサーの画素内は、センサーの画素一つひとつに届いた光を、マイクロレンズで最大限に取り込み、光を検出するフォトダイオードに届ける構造になっています。
高感度にするためには、一つひとつの画素を大きくして、取り込む光の量を増やす必要があります。先に述べたように、私たちは画素のサイズを従来の一眼レフカメラの約7.5倍以上に設定しました。これにより、情報の読み出しに時間がかかるという大面積ならではの課題はもちろん、大きなマイクロレンズの設計やその量産技術などとの苦闘があったわけです。
 フォトダイオード内に多段のポテンシャル構造を設計
フォトダイオード内に多段のポテンシャル構造を設計
例えば情報の読み出しとは、具体的にはフォトダイオードで光から変換された電子を、トランジスタを経由して読み出し回路に誘導することですが、ここに工夫を設けました。天体観測用の巨大CMOSセンサーで培った技術を応用し、電子を流れやすくするために、画素の中に多段のポテンシャル構造を作ることを思いつきました。ただ、段の数や形状、角度など坂道の構造は何万通りもあるわけです。これを膨大な量のシミュレーションにより最適化し、大きな画素でも効率よく情報を読み出せるようにしました。
木戸 滋(きど しげる)
担当:半導体製造技術
1996年に入社し、半導体製造装置のプロセス開発や量産CMOSセンサーの歩留り改善などに携わっている。
モットーは、信汗不乱(一生懸命流した汗を信じれば、心乱れず道は開ける ― 仰木彬オリックス元監督の言葉)。
木戸
超高感度センサーは、他のセンサーに比べて信号レベルが高く出てくるため、ちょっとしたゴミや金属による汚染の影響も大きくなります。量産を行う工場としては、これを徹底的に抑える必要がありました。
新しい取り組みを行う際には、とにかく設計、プロセス、製造で試行錯誤を繰り返すしかありません。関係する開発者が連携しながら、実験を繰り返しました。


発想の転換が生み出した
新開発グローバルシャッター
一般的なCMOSセンサーでは、原理上、高速で移動する電車などを撮影すると、被写体がゆがんで撮像されることがある。グローバルシャッター機能を搭載したCMOSセンサーであれば、こうした現象を防ぐことができるが、その開発は一筋縄ではいかなかった。広いダイナミックレンジも両立したグローバルシャッターの実現につながった、開発者たちの発想の転換とは?
大貫 裕介(おおぬき ゆうすけ)
担当:デバイス要素開発
2007年に入社以来、CMOSセンサーの画素開発およびプロセスインテグレーションに従事。
多角的な視点で物事を捉え、世界に羽ばたく魅力ある製品の開発を心がけている。
「グローバルシャッター機能」を搭載したCMOSセンサーを開発されたということですが、これはいったいどういうものなのでしょうか?
大貫
デジタルカメラやビデオカメラなどの機器で画像を記録する場合、CMOSセンサーの画素に当たった光の強弱に応じて電子がたまり、この電子を読み出すことで画像データが得られます。
一般的なCMOSセンサーでは、ローリングシャッターという方式を採用していて、1行単位で画素の露光と電子の読み出しを行うようになっています。そのため、最初に露光する行と最後に露光する行では、時間差が生じてしまうのです。その結果、走行している電車や回転するプロペラなどを撮影すると、被写体がゆがんでしまったり、撮影中にフラッシュを使うと上下で画像の明るさが異なるフラッシュバンド現象が発生してしまうことがあります。
なるほど、たまにゆがんだ電車の映像を見かけることがありましたが、それが原因だったんですね。
大貫
グローバルシャッターでは、全ての画素が同じタイミングで露光するため、ゆがみやフラッシュバンド現象がなくなります。


どうやって実現しているのでしょうか?
大貫
CMOSセンサー内にある一つひとつの画素は、バケツのようなものだと思ってください。ローリングシャッター方式のCMOSセンサーの場合は、光を受けるフォトダイオードというバケツが1つあり、このバケツから電子を順次読み出していきます。
一方、グローバルシャッター方式のCMOSセンサーには、フォトダイオードというバケツに加え、フォトダイオードの電子を一時的に蓄えるメモリーという2つ目のバケツが用意されています。全てのフォトダイオードのバケツの電子を、メモリーのバケツに同じタイミングで送ることによって、グローバルシャッターは実現されているのです。
しかし、この方法には大きな問題がありました。
どういうことでしょう?
大貫
1つの画素内にフォトダイオードとメモリーという2つのバケツを用意するということは、バケツ1つ当たりの大きさは小さくなりますよね。
例えば10Lのバケツなら、水のない状態から満杯の10Lの状態までを表現できますが、5Lのバケツだと10Lのバケツに比べて表現できる状態が少なくなるわけです。
イメージセンサーの重要な性能指標にダイナミックレンジというものがあります。これは信号の最小値と最大値の比率を指しますが、バケツの大きさだと考えればわかりやすいでしょう。大きなバケツでダイナミックレンジが大きいほど、明るさや色の表現力が広がるのです。
グローバルシャッターとダイナミックレンジをいかにして両立させるか。この課題を解決するために、新しい駆動方式を開発しました。
これまでグローバルシャッター方式のフォトダイオードとメモリーのバケツは同じサイズで開発検討をしていましたが、新駆動方式では、フォトダイオードとメモリーのバケツのサイズや、送り方の方法を工夫しました。
どうやってアイデアを創出したのでしょうか?
大貫
職種関係なく選出されたメンバーで、グローバルシャッターとダイナミックレンジをいかにして両立させるかを議論しました。異なる職種のメンバーが集まることで、議論がかみ合わないこともありましたが、メンバーの発言を決して否定せず、様々な視点をもとにアイデアを作り上げ、そのアイデアをすぐに試作するなどの試行錯誤を繰り返しました。その試作の中の1つが、新駆動方式となります。
何もないところからいきなりアイデアが出てきたのではなく、みんなが苦労して解決方法を考えていたからこそ生まれてきた技術だと思います。


設計、開発、製造の連携が
生み出す新世代のセンサー
急増するイメージセンサーの需要を支えるのは、産業機械や自動車などの新たな分野である。こうした分野で求められるセンサーをいかに素早く開発して、市場に投入するか。一般消費者向けとは大きく異なる市場に向けて、開発者たちのチャレンジが始まっている。
高田 健司(たかた けんじ)
担当:デバイス販売推進
2003年に入社し、有機ELディスプレイの開発を経て、CMOSセンサーの販売推進を担当。
安心・安全・便利な社会に貢献し、人々の役に立つデバイスビジネスの実現をめざしている。
これまでキヤノンは、自社で開発したイメージセンサーを自社製のデジタルカメラなどで使ってきましたが、今後はイメージセンサーを外販していくそうですね。
高田
キヤノンは、2015年1月に販売推進プロジェクトを設立し、今後は外販にも挑戦していきます。超多画素、超高感度のセンサーは、キヤノンの技術アピールとしての側面が強く、比較的ニッチなマーケットを対象としています。
一方、グローバルシャッターは今後産業用カメラのメインストリームになる目玉商品です。
どういうことでしょう?
高田
日本だけでなくアメリカなどでも製造業の国内回帰の動きが広がっています。しかし、人件費の高い先進国で製造を行うためには、自動化してコストを下げることが不可欠です。そのため、製品検査を自動で行うカメラなど、産業用カメラの需要がどんどん伸びていくと考えられます。
産業用カメラ以外では、自動車での需要も増えるでしょう。自動車の国際基準を定めている国連の自動車基準調和世界フォーラムで、2017年6月からドアミラーの代わりに、カメラとモニターの組み合わせで代用することが国際的に認められましたし、緊急時の自動ブレーキ装置の義務化も検討されています。こうした用途において、イメージセンサーは重要な役割を果たすことになります。
一般消費者向けと産業用では、商品企画も変わってくるのでしょうか?
高田
一般消費者向けカメラは人間が使いますが、産業用、自動車用のカメラは機械に組み込まれて使われることになります。産業用機械は24時間365日稼働しても壊れてはいけませんし、自動車は炎天下や零度以下の厳しい環境できちんと動作することが求められます。
キヤノン製イメージセンサーの画質は世界一だと思いますが、今後は画質とともに、耐久性・耐環境性能で優位性を示すことが重要になってくるでしょう。

大貫
今までイメージセンサーは人間の眼で捉える映像を記録するために使われてきました。これからは人間の眼を超える用途で使われることになっていきます。可視光以外の領域を見たり、ものすごく暗いところや明るいところで撮影したり、あるいは超高速で動く物体を捉えるなど、新たなセンシング用途で活躍することになるでしょう。
イメージセンサーの役割が大きく変化していくわけですね。そうした新しい製品を開発していくために、開発者はどうあるべきだと思いますか?またどんな人と働きたいですか?

高田
ワールドワイドの市場を狙い、「世界一になるんだ」という野心を持つ。それが大事ではないでしょうか。
木戸
先ほど話が出ましたが、一般消費者向けと産業用ではイメージセンサーに求められるスペックも変わってきますから、変化に対応でき、新しい分野に飛び込める向上心が必要ですね。
赤堀
製品開発はチームで行うものですから、お互いの状況がどうなっているのか気を配りながら進めないとうまくいきません。自分の専門だけでなく、周りの技術もしっかり理解できる、コミュニケーション能力のある人と一緒に仕事したいと思います。

鳥居
私はプロセス製造技術を担当していますが、入社するまでは半導体の「は」の字も知りませんでした。うちの半導体チームでも半導体を専攻していた人は1割いるかどうか。これからの半導体は、物理、化学、電気など、生物を除くあらゆる分野が関わってきます。いろんな視点を持った人に参加してほしいですね。
大貫
私も大学では機械を専攻して、半導体のことはまったく知らずに入社しました。CMOSセンサーもデジカメだけに使うものではなくなっていますから、異なるバックグラウンドを持っていることは強みになります。鳥居は「生物を除く」と言いましたが、CMOSセンサーの医療応用も進んでいますから、今後は生物の知識も強みになるかもしれませんよ。自分の専攻にかかわらず、やりたいことのある学生さんに来ていただきたいです。
領木
10年間CMOSセンサーを手がけてきて、想定外のトラブルは必ず起こると学習しました。しかし、1人で解決できるトラブルは本当に少ないんです。周りのサポートがあって、初めて解決できる。周りの人を巻き込み、自分も周りをサポートする。そのためにいろんな知識を身につける。そういうギブ・アンド・テークの精神が大事だと実感しています。
インタビューでも語られたように、CMOSセンサーの用途はデジカメに留まらず、あらゆる分野に広まりつつある。人がカメラで思い出の映像を記録するという行為は、CMOSセンサーの用途のうち、もはやほんの一部にすぎない。電子デバイスがリアルな世界を認識し、働きかける時、そこには必ずと言っていいほどイメージセンサーが存在するのだ。
デジカメ市場が縮小しているのは確かだが、それよりもはるかに巨大な市場が生まれている。その市場をめぐり、世界では熾烈な競争が繰り広げられている。
急速に拡大する市場において、多様化するユーザーニーズをいかにつかむか。
キヤノンでは、設計、プロセス、製造の各部門が密接に連携している。ユーザーニーズをくみ取り、迅速に製品化を行う上で、これは大きなアドバンテージだ。果たして、これからどんなセンサーが生み出されるのだろうか?

インタビュアー・構成
山路 達也(やまじ たつや)
1970年生まれ。雑誌編集者を経て、フリーのライター/エディターとして独立。IT、科学、環境分野で精力的に取材・執筆活動を行っている。
著書に『アップル、グーグルが神になる日』(共著)、『新しい超伝導入門』、『Googleの72時間』(共著)、『弾言』(共著)など。