光の粒のような高速で動くものをとらえることが可能な「SPADセンサー」。その優位性にいち早く着目し、スイスへの留学を経て世界初100万画素のSPADセンサーを開発し、イメージングの新たな可能性を切り拓いた開発者に聞きました。
※ SPADセンサーにおいて。2020年6月23日現在。キヤノン調べ。
https://global.canon/ja/news/2020/20200624.html
2013年の入社直後から、カメラなどに広く使われるCMOSイメージセンサーの開発に取り組むなかで、情報収集のために読んでいた論文の中で目に止まったのがSPAD(Single Photon Avalanche Diode)センサーでした。「CMOSセンサーとはまったく異なる原理で撮像を行うセンサー」という点に興味をもち、関連論文を読み進めるうちにその魅力に引き込まれていきました。
― SPADセンサーのどのようなところに惹かれたのですか?
SPADセンサーの魅力は、光の最小単位である光子(以下、フォトン)を一つひとつ数えることができるしくみを採用していることです。そして、そのフォトンを瞬時に最大100万倍に増幅でき、増幅時のノイズ発生も抑えられることから、闇夜などの暗い環境下でも撮像できることに大きな可能性を感じました。
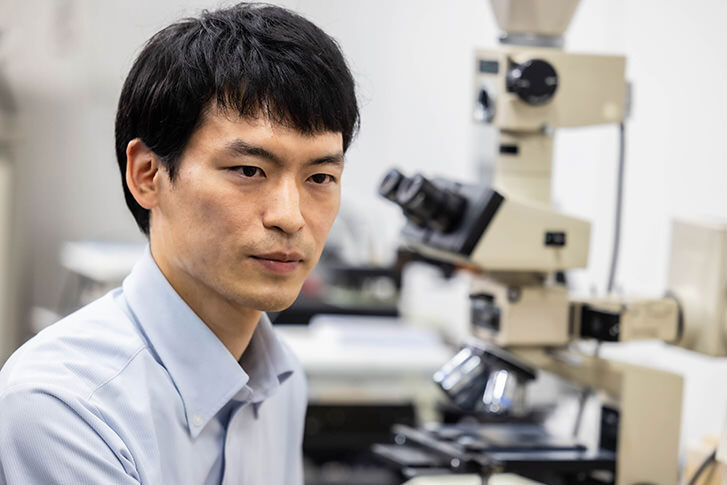
趣味の天体観測などでキヤノンのカメラを愛用していたことからキヤノンに興味をもち、2013年に入社。以来、イメージセンサーの開発に携わる。SPADセンサーの開発において世界初の偉業を達成し、イギリスの科学雑誌「Nature」で「ナノサイエンスを再構築する4名の若手研究者」の1人に選出。
私は物理学が好きで、高校生の時から、光の性質には波と粒子の二面性があるというアインシュタインの説に興味をもっていました。SPADセンサーを研究すれば光の二面性についてより深く理解できそうだと感じました。
入社以来開発に取り組んでいたCMOSセンサーは、多くの先輩たちが長年研究に携わっていて、今後、その技術レベルまで自分が追いつけたとしても、追い抜くことは難しそうだと感じ、どうしたら会社に貢献できるか悩みました。そこで、新しいSPADセンサーの技術を自分のものにしてみたいと考えるようになりました。
当時は社内で「SPAD」という言葉すらほとんど知られていない状況で、上司にSPADセンサーの開発をはじめたいと提案し、技術調査がスタートしました。最初は1人からスタートした調査ですが、周囲にその将来性や研究の必要性を伝えていき、徐々に携わる人数も増え、検討も加速しました。
入社した時から海外で仕事をしたいという気持ちがありました。SPADセンサーと出会ってから、最先端の学術機関で理解を深めたいという思いも加わり、留学を希望しました。留学先はSPADセンサー研究で最新の研究を行う拠点の1つであるスイス連邦工科大学ローザンヌ校(以下、EPFL)。EPFLは、2003年に世界で初めて、CMOSセンサーと同じ量産型の半導体製造プロセスを使ってSPADセンサーを開発した研究拠点です。
― 留学先ではどのように研究を進めていきましたか
入学時に与えられた研究テーマは、まだ世界のだれも成し遂げていない「100万画素のSPADセンサーの開発」です。指導教官のシャルボン教授からは大きなビジョンのみを示され、日々の研究の進め方は、基本的にすべて私に委ねられました。
キヤノンでは、上司と相談しながら仕事を進めることが多かったのですが、EPFLでは教授とディスカッションをしてアイデアをもらうことはあっても、具体的な研究の進め方は「自分で考えてやってね」というスタイル。初めは戸惑いもありましたが、試行錯誤しているうちに自ら課題を設定し、解決策を見つけるプロセスを徐々に楽しめるようになりました。

留学先のスイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)
EPFLに入学した当時、SPADセンサーには、画素を小さくしにくいという原理的な課題がありました。100万画素のSPADセンサーの実現というのはシャルボン教授の夢でもあり、自分が在学している間に何としても、教授に成果として届けたいという思いがありました。
SPADセンサーを小型化するために、半導体デバイスの物理特性にもとづくアプローチと、回路に関わる電気的なアプローチ、さらに光に関わる光学的なアプローチなど、すべて組み合わせて可能な限り画素を小さくしながら、性能も向上させることをめざしました。半導体、電気、光学はすべてキヤノンが得意とする分野です。キヤノンで研究して培った経験を大いに生かすことができました。
― 100万画素SPADセンサーのプロトタイプ「Mega X」を初めて動かした時、何を思いましたか。
イメージセンサーの開発では実際のチップを基板に取り付けて、画像が取得できればまずは成功と言えます。ソフトウエアを使用したシミュレーションを入念に行って準備し、最初の実験では100万画素SPADセンサーのうち50万画素の取得に成功しました。目標達成に向けて大きな前進であり、朝方の誰もいない研究室で自分のピース姿を撮れた時のことは今でも忘れません。

はじめて50万画素の撮影に成功した際、まず試しに撮影したのが誰もいない空っぽの研究室。それではつまらないと思い2枚目に自撮り写真を撮影。
一方で、この時100万画素の画像の取得にはいたらず、自分の行ったセンサー設計にミスがあったのではという思いもよぎりましたが、トライアルアンドエラーを繰り返して電気基板に原因があることが判明。この問題をクリアしてようやく100万画素SPADセンサーのプロトタイプ「Mega X」が完成しました。必ずできると信じて開発を行いましたが、初めて試作品を手にした時は、留学期間も残り2~3か月であったこともあり、かなり緊張しましたね。もし、うまく動かなければ自分の留学期間の2年間が全部無駄になってしまいますから。
― SPADセンサーは光の動きそのものも見ることができると聞きます
100ピコ秒(100億分の1秒)レベルの非常に短い時間単位で情報を処理できるため、光の粒のような超高速で動くものの動きをとらえることも可能です。帰国が迫っていた中で研究室の同僚と最後に思い出づくりになるような面白い動画を撮影しよう、ということで撮ったのがこの映像です。
森本さんが研究室のメンバーと撮影した、光の軌跡のスローモーション動画
(出典:スイス連邦工科大学 ローザンヌ校およびキヤノン)
1秒間に地球7.5周分(約30万km)という速さで動く光の軌跡をスローモーションで捉えることができ、感動しました。
しかも、この動画をよく見てみると途中で光の速度が変わっているように見えるんですね。これは宇宙物理の世界で知られている現象で、何万光年も離れた天体でしか観測されたことがなかったのですが、これを実験室内で観測できたことに驚きました。SPADセンサーの実力と将来性を改めて感じました。
スイスから日本へ帰国後、キヤノンに戻ってからも引き続きSPADセンサーの開発に携わりました。その後、キヤノン内のさまざまな部門の技術力・ノウハウもあわさり、高画素かつカラー撮影が可能なSPADセンサーを搭載したレンズ交換式超高感度カメラ「MS-500」の製品化が実現しました。
留学前、上司にSPADセンサー開発の提案をした際、「この技術が製品化される可能性は10%くらいかな」と言われました。「10%しかないのか」と問いかけると、「10%もあるんだ」と言われたのが今でも印象に残っています。新しい技術を製品化するということがいかに難しいかを当時から知ることができていた分、製品化が実現した喜びもひとしおでした。

世界初※1のカラー撮影用SPAD センサー搭載超高感度カメラ「MS-500」。約320万画素1.0型SPADセンサー※2を搭載。闇夜の遠方でも低ノイズで視認性の高いカラー映像を撮影できるので、沿岸の警備、発電所などの重要インフラ施設や河川の氾濫などの監視に活用可能です。
※1 カラー撮影用のSPADセンサー搭載カメラとして。2023年7月31日現在。キヤノン調べ。
※2 総画素数約320万画素/有効画素数約210万画素。
https://global.canon/ja/news/2023/20230403.html

MS-500で、約5km先の海上を航行する夜間の船を撮影。望遠性能に優れたキヤノンの放送用レンズCJ45e×13.6B IASE-V Hを使用。
― 留学から戻ってきて感じたキヤノンの強みとは
独自のSPADセンサーを搭載したMS-500の製品化は、キヤノンが長年培ってきた、多岐にわたる事業のノウハウがあってこそだと感じています。キヤノンは、SPADセンサーをはじめ、放送用レンズ、カメラの映像エンジンなどを自社で開発しているので、それらの特性を深く理解している人材が多く在籍しています。こうしたバックグラウンドを十分生かすことで、センサーやレンズの性能の良さを引き出しつつ、解像感や階調・色再現性の基本性能を上げるなど、各関連部門との連携により高性能な製品を実現しています。
SPADセンサーの次の狙いは、より小さく・高画素化することです。技術をもっと高め、より小さいセンサーで、より高解像度のセンサーおよびカメラを実現することをめざしていきたいです。それにより、キヤノンがつくるカメラの可能性をよりひろげ、世の中をより便利に、豊かにしていていけたらという目標があります。
― 昨年、Nature誌の「ナノサイエンスを再構築する4人の若手研究者」※の1人に選ばれ、キヤノンが新たに設けた「高度技術者認定制度」のトップサイエンティスト 第一号にも認定されました
※出典:「Four rising stars who are reshaping nanoscience」(2022年8月10日)
世界トップレベルの科学誌として知られるNature誌に認めてはもらったことは正直驚きで、最初は人違いかと思いました。誇らしい気持ちと同時に、もっとがんばらねばという思いです。社内からも期待してもらえていると感じていますし、正直プレッシャーもかなりあります。
留学中は一人で研究を進めたことがよい経験となりましたが、個人的にはチームでさまざまな意見を出しながら進めていく方が向いていると思っています。これからはもっと部門や、本部をまたいだ、より大きなプロジェクトを進めて大きな成果を出していくことに注力していきたいです。将来的には大きなチームを率いて世界中をあっと驚かせるような技術や、製品を生み出したいと思っています。